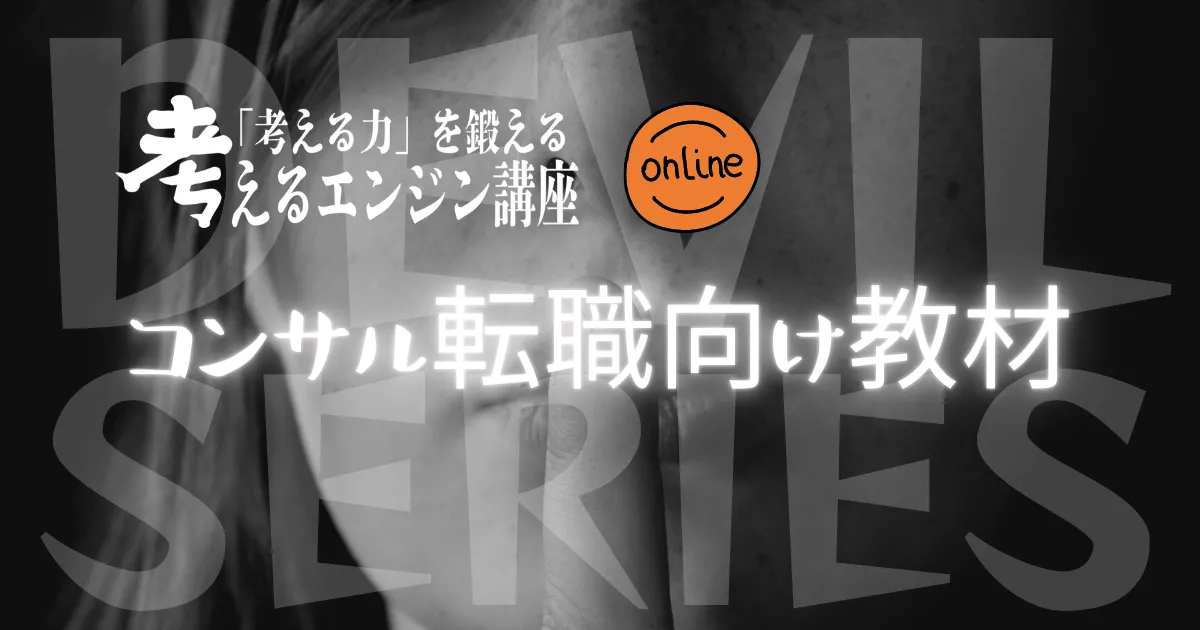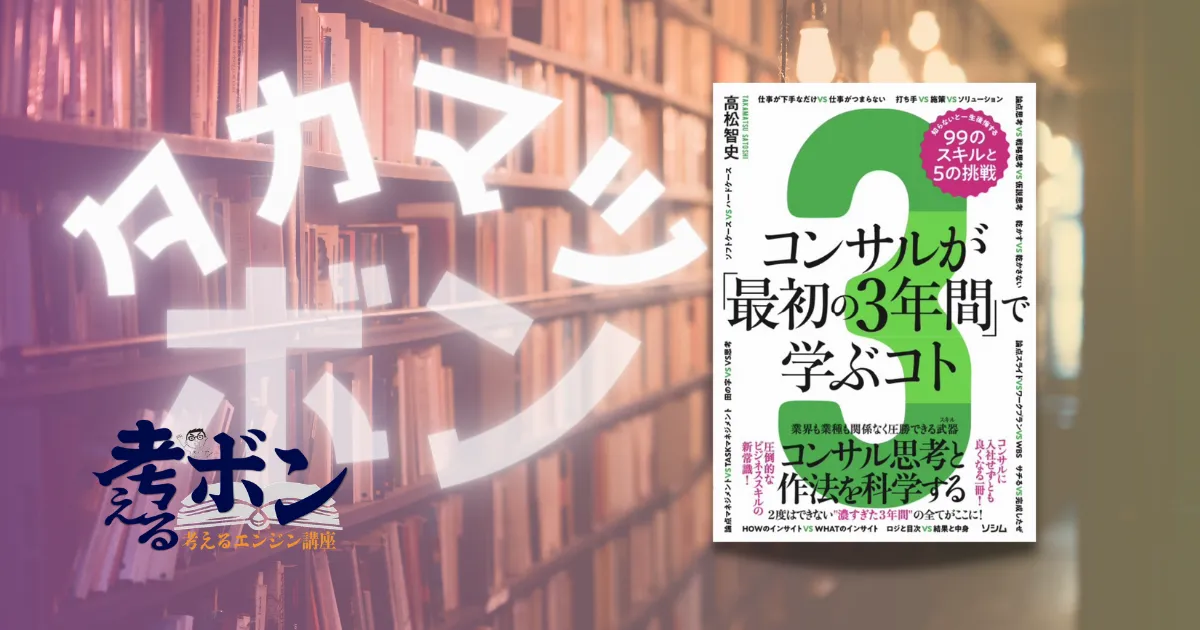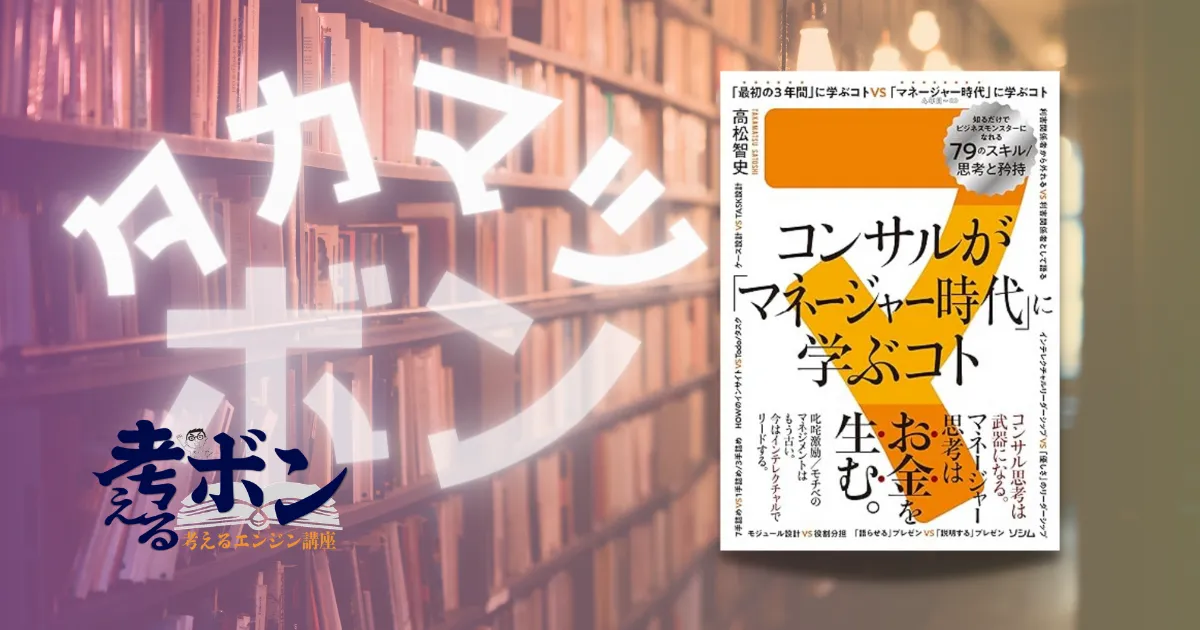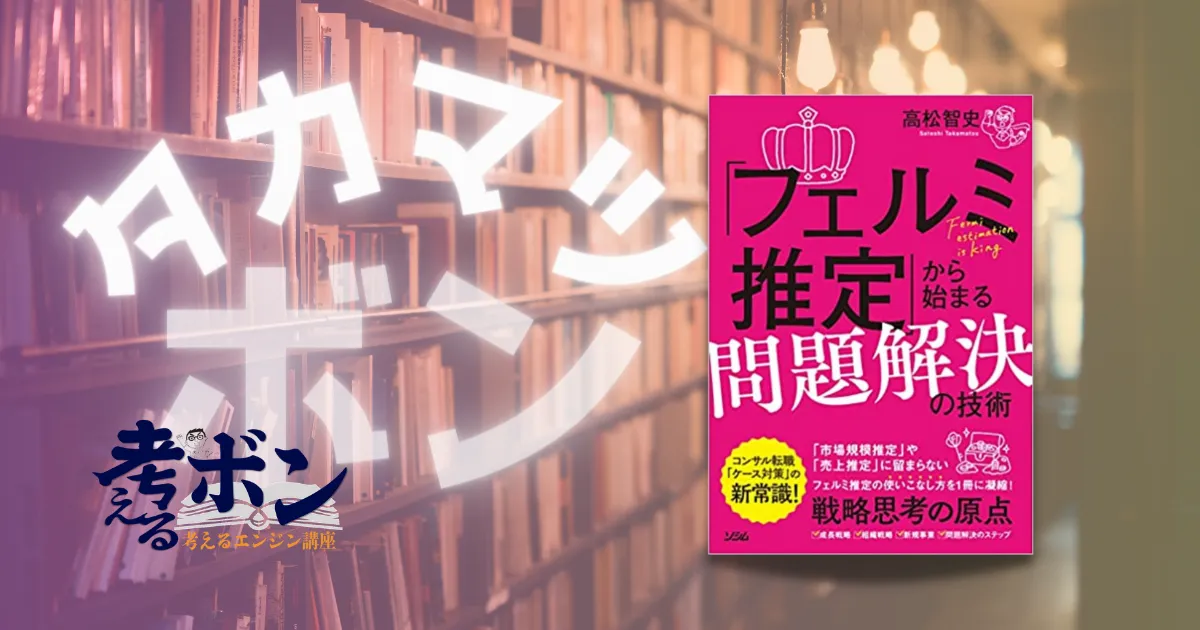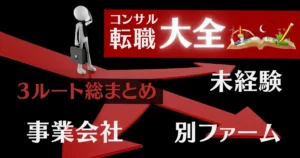コンサル転職大全!未経験・別ファーム・事業会社への3ルートを総まとめ

コンサルタントへの転職を目指す人にとって、「コンサル業界は本当に転職しやすいのか?」は気になるテーマです。未経験からコンサルを目指す場合もあれば、既にコンサルで働きながら別のファームを志望するケース、そして当事者視点を求めて事業会社へ転身する人も少なくありません。
本記事では、「未経験からコンサルへの転職」、「コンサルからコンサルへのファーム転職」、「コンサルから事業会社への転職」という3つのルートについて、それぞれの特徴や成功するためのポイントをまとめています。あなたのキャリア計画にフィットするルートが見つかるよう、じっくりと参考にしてみてください。気になるトピックがあれば、目次をクリックすると飛べます。
未経験からコンサルタントに転職する場合
コンサルは中途採用が中心。高倍率に挑むための前提理解
コンサルティング業界では、新卒採用よりも中途採用が主流という特徴があります。ファームによっては、業界未経験者も含めて積極的に採用していますが、どのファームも求める人物像は明確です。実務や専門分野での経験を活かせる人材、あるいは高いポテンシャルを示せる人材が多く合格を勝ち取っています。
特に戦略系ファームでは選考倍率が非常に高く、50〜100倍に達するケースも珍しくありません。景気に左右されない基準の厳しさは、コンサル業界特有のものと言えます。たとえ不景気になっても、最低ラインの水準は維持され、優秀な人を逃さない選考が行われるのです。
このような厳しい選考を突破するには、しっかりした事前準備が欠かせません。もし現在の職場で成果を上げてから転職するプランを立てているなら、次の応募まで数年かかるリスクも考慮に入れる必要があります。転職の時期やタイミングは、事前に十分見極めることが重要です。
戦略系コンサルティングファームを目指すなら、最初は別ファームで2〜3年実績を積むのが良い
戦略系のトップファームを目指す場合、いきなり最難関に挑むよりも、まず別のコンサルファームに入り、2〜3年でマネージャー層に成長する道も有効です。
この数年のあいだに、エンゲージメント管理や戦略立案などの実務経験を積み、さらに「コンサルでの仕事の進め方」を把握しておくことで、自分の市場価値を格段に高められます。
その結果、「〇〇ファームでマネージャーとして活躍しているのなら、戦略系ファームでも即戦力だ」と評価され、転職がグッと現実的になるのです。

コンサルが「最初の3年間」で学ぶコト
「戦略思考」 =「解、答え、意見、メッセージ」を作り出す考える技術を、「暗記する」=「考える際に自分に問う、声に出して唱える」フレーズを覚えるだけで身につけられる 「思考技術」の本です。
中途入社ならではの高い期待と即戦力志向
コンサルファームに中途採用で入社する場合、新卒と違い、すでに一定の業務経験を持つ即戦力として期待されることが多いです。たとえ未経験枠であっても、入社後は「優秀で生意気な同僚たち」と肩を並べ、同じ土俵で成果を出すことが求められます。そのためには、プライドを抑え、焦らずスキルを磨く姿勢が不可欠です。
最初は混乱することも多いかもしれませんが、コンサル業界は伸びる人には惜しみなく成長の場を与えてくれます。選考を通過する実力と覚悟があれば、現場で十分に力を発揮し、短期間で頭角を現すチャンスも少なくありません。
選考を突破するために、入社後をイメージして準備
- 1. キャリアプランの明確化
コンサルは意外にも転職が多い業界です。転職後もどんなキャリアを歩むか、ある程度の指針を持っていると評価されやすくなります。 - 2. 選考倍率の高さを前提にした対策
難易度が高いからこそ、ケース面接や論理的思考のトレーニングは必須。事前に書籍やオンライン講座などで学ぶことをおすすめします。 - 3. 即戦力以外の魅力の打ち出し
未経験であっても、前職でのリーダー経験や業界知識、コミュニケーション能力など、強みを明確に示すことがポイントになります。
キャリアや志望動機をどう語るかで、面接の通過率は大きく変わります。特に「なぜ今、コンサルなのか」をロジカルに説明する力が問われます。詳しくは、キャリアの語り方に特化したこちらの記事もご参考ください。

適正年齢とキャリア段階。転職成功のタイミングを見極める
コンサルの世界は、年齢によって期待される役割が大きく変わります。20代半ばであれば柔軟性やポテンシャルを評価されやすく、30代前後では即戦力としてのスキル発揮が求められ、35歳以上になると専門分野でリーダーシップを発揮することが重要になります。
自分の年齢やキャリア段階に合わせて「どのファームに」「どのポジションで」入社すべきかを、戦略的に考えるのが、未経験からのコンサル転職成功への近道です。
学歴よりも実務力と考える力が鍵だが、最初の選考は例外
コンサル業界では、どんな学歴を持っているかよりも、入社後の実務やプロジェクトで成果を出せる人材が評価されます。ただし、書類選考や一次面接の段階では、出身大学や院の情報が補助的に使われるケースが少なくありません。
とはいえ、実際に入社してしまえば学歴を持ち出されることはほぼなく、問題解決能力やロジカルシンキングといった考える力が唯一にして最強の武器となります。学歴に自信がない人は、現在の職場で実績を積む、もしくは具体的な資格取得や勉強会参加などで補強しながら挑むのが得策です。
転職における業界知識と資格の扱い
業界経験がある場合、その分野のバリューチェーンや主要企業動向をどこまで把握できているかが面接でチェックされます。特に金融業界出身なら、競合他社の状況やマーケット全体の変化を語れるかどうかが重要となります。
資格はあって損はないが、決定打にはなりにくい
医療関連の有資格者が医療系の案件で重宝される例などを除けば、コンサルファームにとって最終的な判断材料は資格よりもやはり実務力、そしてロジカルシンキングです。たとえば会計士やMBA保有者であっても、それだけで合格が確約されるわけではない点には注意が必要です。
志望動機とケース面接に緻密な準備が必要
志望動機は、「なぜそのファームなのか」と「自分がいかに賢く戦略的に物事を考えられるか」を、論拠をもって示す場です。単なる熱意ではなく、確固たるロジックを面接官に示しましょう。また、ケース面接対策では、フェルミ推定や構造化思考を徹底的に学び、会話形式で論点を深めるトレーニングが欠かせません。
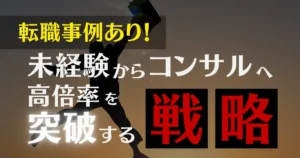
コンサルからコンサルへ!他のファームに転職する場合
コンサルからコンサルへ転職する最適なタイミングとは
コンサルファームで3年ほどキャリアを積むと、「より戦略寄りの案件に挑戦したい」「今の案件がITやPMOに偏りがちでもっとビジネス感のある仕事をしたい」など、さまざまな思いが湧き上がるものです。いわゆるMBBなどの戦略ファームを志望するケースもあれば、単純に「もう少し別の分野で腕を振るいたい」という場合もあるでしょう。
しかし、「今すぐ辞めて転職活動を始める」よりも、まず現在のファームでマネージャーまで上り詰め、そこから転職を考えるほうが得策なケースは意外と多いです。ここでは、その理由や準備の仕方、ケース面接での注意点をまとめていきます。
マネージャーになってから転職するメリット
コンサル業界では、「コンサルファームのマネージャー職」という肩書きの価値が非常に高いです。特に、所属先が総合系ファームやIT寄りのファームであっても、「マネージャー」という立ち位置自体に一定の評価がつく傾向があります。
もし、環境がよほど耐え難い状態(パワハラなど)でなければ、あと2~3年、今のファームでしっかりマネージャー昇進を勝ち取ってから転職に挑むのがおすすめです。
コンサルが「マネージャー時代」に学ぶコト
10万部を超えた『コンサルが「最初の3年間」で学ぶコト』の続編であり完結編にして、過去最高傑作。400ページにもわたる至高の “熱き講義形式” ボン。
コンサルタントが『マネージャー時代』に学ぶコト、学ぶべきことを詰め込んでおります。
マネージャー昇進までの2〜3年をどう過ごすかが重要
マネージャー候補として過ごすこの2~3年は、「ただなんとなく案件を回す」だけでは非常にもったいないです。
論点思考や戦略思考を日常のプロジェクトで使いこなし、IT監査やPMO業務であっても、いかに戦略的に考え抜いて価値を出すかを追求することが、後々のケース面接でも大きな武器になります。

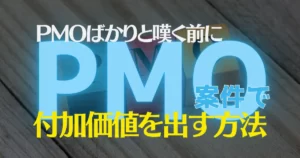
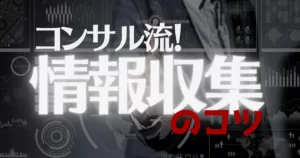
ケース面接ではコンサル力を一発で証明せよ
コンサルからコンサルへの転職では、面接官(同じくコンサルのマネージャークラス)が「どの程度、コンサルらしい思考やアウトプットを当たり前に出せる人か」を厳しく見てきます。
「○○ファームでマネージャーしていた」と言っても、面接官からすれば「どれほどのもの?」という目線で最初のケース面接に臨むことが多いです。ここでホームランを打てるかどうかが採否を大きく左右します。

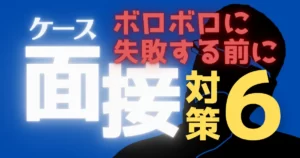
「フェルミ推定」から始まる問題解決の技術
「フェルミ推定」は、市場規模推定や売上推定を算出する為だけの思考法じゃありません。成長戦略、新規事業などに幅広く応用できる、いわば戦略思考の原点とも言えます。そして、その考え方を丸っと凝縮して一冊にまとめたのが本書です。
戦略ファーム面接官の心理
- 「すでにコンサルなんだから、特にマネージャークラスならケース面接で文句なしのパフォーマンスが出て当然」と考えている
- 事業会社出身者のように「コンサル未経験なのである程度OK」という甘さは一切ない
つまり、冒頭で出題されるケースに対して、いかにもコンサルらしい論点展開や「クライアントと議論するときはこうなる」という流れを見せつけないと、不合格になる可能性が高いです。
実際にアクセンチュアからBCGへ「サクッと」転職した例
未経験者の中途転職ではなく、すでにコンサルファームに所属している人が「最速でマネージャーへ昇進」「その年に転職活動」というプランを実践したAさん(仮名)の事例があります。
彼はIT寄りのプロジェクトをメインに担当しながらも、論点思考や戦略思考を使いまくり、プロジェクトで抜群の成果を出し続けました。結果、マネージャーに昇格した直後に複数の戦略ファームを受け、ほぼ全勝という形で内定を獲得。BCGからオファーを引き出し、スムーズに転職を果たしたのです。詳細は、以下の記事を参照してください。

マネージャーとして転職する際の3つの注意点
- マネージャーを目指す2〜3年の間に論点思考を習慣化
昇進目前の立場なら、いまの案件がどんな内容であれ戦略的に考え抜く癖をつけましょう。後日、面接で問われるのは、その2〜3年で「どういう形で考え、どう成果に繋げたか」という具体的エピソードです。 - 戦略ファーム面接官の突っ込みに耐える
「IT寄りプロジェクトしかやっていないんでしょ?」という先入観を壊すには、面接でのインパクトあるケース回答が必須。数問のケースに対して、コンサルの王道手法を短時間で示す必要があります。 - ポストコンサルの展開まで想定
戦略ファームに移ったあと1年でシニアマネージャーへ…といった話もありえます。転職前から「そこで何をしたいのか」をイメージし、自分ならではのアピールができると強いです。

コンサルから事業会社に転職する場合
コンサルから事業会社に転職するポイント
コンサルタントとしての論理思考やプロジェクト推進力は、実は事業会社でも大いに活用できます。短期的な成果を得るのが得意なコンサル出身者が、長期的にビジネスを育てる現場に移ることで、どのようなシナジーや壁が生じるのか。本記事では「コンサル→事業会社」へのキャリアチェンジを検討する際に押さえておきたい主要ポイントを、志望動機やメリット・デメリット、実際に活かせるスキルなどに分けて解説します。
コンサルと事業会社の意外な共通点
コンサルファームと事業会社は、一見やり方や文化が大きく違うように見えるかもしれません。しかし最終的には、どちらも「社会や顧客に価値を提供する」ことを目指しており、そのために専門的な力を掛け合わせ、チームとして成果を上げる点が共通しています。
短期の戦略提案に注力するコンサルと、長期的な事業育成に注力する事業会社の違いこそあれ、「現状をよりよく変えていく」という向上心が組織を動かす原動力になっているのはどちらも同じです。
コンサルと事業会社の決定的な違い
プロジェクトスパンと成果の出し方
- コンサル:3~6か月のプロジェクトが中心。終了と同時にチームが再編されることが多く、短期間で成果を求められやすい
- 事業会社:同じメンバーと長期スパンでビジネスを育てる。会社全体としても中長期の視野が重視されやすい
コンサル時代は、素早く結果を出すというプレッシャーと引き換えに、担当プロジェクトが終われば新たな案件へ移行するといったリセットがやりやすい環境。一方、事業会社では、自分の決定や行動が数年越しで組織や製品に影響するため、長期的な視点とコミットメントが求められます。
個々のスタンスと意思決定プロセス
- コンサル:客観的・中立的アドバイザーとしてロジックを追求しやすい
- 事業会社:自社のビジョンや社内のしがらみ、人間関係など、より現場に根ざした現実を考慮する必要がある
コンサル時代は、クライアント企業へ提案を提示するだけだったとしても、事業会社では「自分たちが決めたことを自分たちで実行する」場面が増えます。その際、社内政治や部署間対立、ステークホルダーとの調整など、論理だけでは解決できない局面に直面することも珍しくありません。
コンサルから事業会社への転職志望動機
コンサルから事業会社に移る方には、以下のようなモチベーションを抱えているケースが多いです。ここでは代表的なメリットを中心にお伝えしますが、実際の転職活動ではさらに具体的なエピソードと結びつけることが大切です。
- 当事者としての手応えを得たい
コンサル時代は提案や戦略が実行されるかはクライアント任せで、成果を直接感じられないこともありました。事業会社なら自分が立案・実行し、結果をダイレクトに売上・ユーザー数などで確認できるため、達成感が大きいという利点があります。 - 長期的なビジョンでキャリアを築ける
コンサルは短期成果重視の色が強いのに対して、事業会社では持続的な事業拡大や組織づくりを見据えて動けるため、マネジメントや経営幹部候補として成長する道が開けます。 - 実行フェーズでの裁量が大きい
コンサルでは社内外のステークホルダーに振り回されることもありますが、事業会社では自身のアイデアを自社プロダクトに素早く反映しやすい場合が多く、「試しながら学ぶ」プロセスが加速しやすい環境と言えます。 - 組織の顔としてリーダーシップを発揮できる
コンサル時代はクライアント企業の決定をフォローする立場でしたが、事業会社では経営幹部候補や事業責任者として、自らの意思で組織を動かすことが可能。これはプレッシャーでもあり、やりがいにも繋がります。
コンサルから事業会社に行くデメリット
もちろん、期待通りにスムーズに動かない局面や、思わぬストレスを抱えることもあります。
- 短期的に成果を出すプレッシャー
コンサルタント出身者は即戦力扱いされやすく、なかには短期間で大きな実績を上げることを求められるケースも。30代後半以降で転職すると、マネジメント面の期待も一気に高まります。 - 内部調整の煩雑さ
プロジェクトが遅れる原因がシンプルなロジック不足ではなく、「社内の利害」「部署間の軋轢」「古くからの慣習」だったりすることも。コンサルの提案型スタイルが通じない場面が多く、思い通りに進まないことがあります。 - 給与・ポジションダウンの可能性
コンサルは業界トップレベルの給与レンジを誇りますが、事業会社では必ずしも同水準の待遇が得られるとは限りません。スタートアップや新規事業の立ち上げに関わる場合はなおさらで、株式報酬やインセンティブで補う仕組みが一般的になることも。 - 何でも自分でやる場面が増える
コンサル時代は専門チームが行ってくれた資料作成や市場調査など、さまざまな業務を自分でこなす必要が出てきます。一見雑用に見える分野で踏ん張らないとプロジェクトが前に進まない場面も多々あります。
事業会社への転職で役立つ志望動機の考え方
「事業会社への転職を考えている」コンサルタントにとっては、熱意だけでなく、いかに自分の論理的思考や実務スキルが‘御社で生きるか’を示すことが重要です。単に「経営に携わりたい」「長期視点で成果を出したい」だけでは弱く、企業ごとのビジョンや戦略にどのように貢献できるかを具体的に組み立てる必要があります。
志望動機が重視される理由
事業会社は、コンサルよりもさらに当事者意識を持った人材を求める傾向が強いです。どれだけ会社の方向性を理解し、そこに自分のスキルを掛け合わせる気概があるのかを見極めようとします。特に経営企画や新規事業、幹部候補採用などの場合、論理的な根拠に基づく志望度の高さが採用の決め手となることが少なくありません。
何を見られているのか―ロジックの組み立て方
事業会社でも、自分の考えるプロセスに注目される点はコンサル選考と似ています。「なぜこの業界・企業なのか?」「自分の強みや過去の案件経験をどう活かすのか?」を、情報収集や自分なりの分析に基づいて論理立てて語れるかがポイントです。
- 企業研究
- 公式サイトやIR情報、社長インタビュー、プレスリリース等をチェック
- 業界レポートや競合他社の動向を参照し、その企業ならではの強み・課題を整理
- 自分の強み・実績の棚卸し
- コンサル時代にどんなプロジェクトを担当し、どんな成果をあげたか
- 新規事業や組織改革、ユーザー目線でのサービス改善など、具体的エピソードを洗い出す
- 両者を結びつけたロジック構築
- 企業の今後の方向性と自分の実績・強みの交点を探り、志望動機として言語化
- 「ここで働きたい理由」と「自分が貢献できる具体的なシーン」を筋道立てて示す
志望動機でアピールしたいポイント
- コンサル時代に培った論理思考が活かせること
- 自分が如何に短期的な課題発見や成果創出に強いのかを、数字や実績で語る
- 「この企業でなら、提案と実行を一体でやり切れる」と、当事者意識をアピール
- 御社でなければならない具体的理由
- 競合との比較ポイントを示し、なぜその会社の業界位置づけやプロダクトに魅力を感じるかを論理的に説明
- 第一志望であると明確に伝え、相手の期待度を上げる
- 自分の強み+企業の課題を結びつけたストーリー
- たとえば、「これまでの分析力とPMO経験を活かし、新規事業×海外市場進出の両輪で成果を狙いたい」といった形で、具体的課題と自分の得意分野を結びつける
コンサルから事業会社に行く時に意識すべきこと
コンサルから事業会社への転職を成功させるには、いくつかの心構えが重要です。特に30代後半以降は家族の事情や年収面などハードルが高まるので、下記ポイントを参考に自分に合った進め方を模索してください。
自分の安全網を整えておく
- 収入・生活面の余裕
コンサル時代より年収が下がる可能性も高いため、事前に十分な貯蓄を持っておくと転職後に挑戦しやすくなる - 戻る先を確保
前職で築いたネットワークやコンサル転職マーケットの強みを活かし、もし失敗しても再びコンサルに戻る道を意識しておく
役職や肩書きにこだわりすぎない
- ポジション交渉の現実
CXOクラスなど魅力的な役職で呼ばれることもあれば、いきなり肩書きダウンする場合も。どちらが自分のキャリアにメリットか冷静に判断する - 肩書きより実績
最終的には入社後どれだけ成果を出せるか。コンサル時代と評価軸が異なる面を理解し、成果を数字で見せるよう意識
年齢が上がるほど即戦力・リーダーシップが必須
- 20代~30代前半:ポテンシャル採用枠も十分あり
- 30代後半以降:幹部候補として成果をすぐ出すことを求められ、逆に言えば大きな裁量やマネジメント経験を積めるチャンスもある
部分的なお手伝いから参画する選択肢
- 副業やアドバイザー契約
いきなり本業を辞めずとも、週末やアドバイザーとしてスタートアップや事業会社をサポートし、その感触を確かめる方法がある - 会社側にとってもメリット
部分的に関わる中で相手企業のカルチャーを理解しやすく、お互いにミスマッチを減らせる
失敗しても大丈夫なメンタリティ
- コンサルの市場価値は高い
一度事業会社で挑戦しても、万が一合わなければ再度コンサルへ転職しやすい - 長期視点を持つ
一つの失敗や挫折はむしろ貴重な学習経験。新しい事業アイデアや別分野へのシフトに活かせる
コンサルの経験が事業会社で活かせるスキル
仮説検証型の問題解決力
事業会社では、完璧な情報が揃わない中で意思決定する場面が日常的に存在します。コンサル出身者が得意とする「まずは仮説を立て、必要なデータや検証方法を考え、学びながら方向修正する」流れは、スピーディーな意思決定を促し、ビジネスの加速に直結します。
一歩踏み込むコミットメント
コンサル時代はあくまでクライアントの立場をサポートする存在でしたが、事業会社では自分が当事者として最終責任を負います。コンサルでいうクライアントを納得させる力は、事業会社では「社内外を巻き込み、泥臭くてもやり切る力」に転化できます。
ロジカルシンキング & わかりやすい資料作成
コンサルが培った論理展開やドキュメント作成の速さは、事業会社でも強みになります。特に事業会社では、社内外の説明や稟議などが多く、短時間で関係者を説得する必要があるので、論点をパッと整理し、簡潔なスライドを作るスキルは非常に重宝されます。

マネジメントの基礎力(プロジェクト推進、タスク管理)
短納期で成果を出すコンサルの環境で磨かれたプロジェクト進行力は、事業会社でも「期限に間に合わせる」「チームをまとめ上げる」といった場面で活かしやすいです。特にスタートアップなど、スピードが求められる現場では、コンサルのタスク管理やリーダーシップが即戦力となります。
脳内の仮想上司/クライアントを使いこなす
コンサル時代に上司やクライアントの思考法を学んだり、フィードバックを受けた経験を、転職先でも活かすという手法です。新たな組織で悩んだときにも、「前の上司ならこう考えるだろうな」「あのクライアントならこう突っ込むはず」と頭の中で問いかけることで視点を増やし、決断の助けにできます。
事業会社でさらにステップアップするために
1. 枠にとらわれず行動し、感情を理解・使いこなす
事業会社では、短期売上や利益といった数値目標だけでなく、長期的な人材育成や組織づくりも不可欠。その両方を両立するには、コンサル的な「どんな手段でも成果を出す」柔軟さと、周囲の感情に寄り添うコミュニケーション力が大切です。
たとえば、プロジェクトの停滞原因が単なる情報不足だけではなく、「実は誰かが本音で反対している」ことに気づいてフォローすると、スムーズに事態が進むケースも。感情をあえて武器にして、問題発見やメンバーのモチベーション向上に繋げられます。
2. ビジネスサイド視点+エンジニア的目線で新価値を創出
コンサルタントの戦略思考に、エンジニア的な実装目線が加わると、技術と経営レベルのギャップを埋めることができます。新規サービスや製品の開発ロードマップを考える際、「実際に開発可能な要件か」「ユーザー体験を重視できるか」といった実用的な視点まで踏み込むと、社内外から高い納得感を得やすいでしょう。
3. プロセスから結果重視へ切り替え
コンサルの評価は論理プロセスの正しさも大きな要素ですが、事業会社では成果指標(売上やユーザー数など)がモノを言います。いかに優れた戦略や提案を作っても、結果に繋がらなければ評価されないのが現実。「すぐに方向転換する決断力」「必要なら泥臭い手段も厭わない」「周囲に頭を下げて助けを求める」といった柔軟さが求められる場面も多いです。
4. 頭の中にストックし続ける
コンサル時代に覚えたフレームワークや先輩からのアドバイスを、常に頭の引き出しにしまい込んで活用できる人は、事業会社でも圧倒的に動きが早いです。日々のプロジェクト終了時や週末などに、簡単なメモや振り返りを行い、学びを自分なりに整理する習慣を続けるのがおすすめ。
転職後も過去に学んだ考え方や先輩の口癖を思い出し、意思決定に活かせる人は、組織の中で幅広く信頼されるようになります。
5. 70点でまず動き、走りながら検証実行力
コンサルの完璧主義を一旦捨てて、70点でも動きながら方向修正するアプローチは事業会社で特に効果的です。顧客やユーザーの反応を見つつ、KPIに合わせて改善を回すサイクルを迅速に回せるようになれば、市場の変化にも素早く対応できるでしょう。
6. チームを巻き込み、意見を取り入れる
事業会社で成果を出すには、各部署やステークホルダーとの合意形成が欠かせません。自分のロジックだけで突き進むのではなく、あらかじめ叩き台を準備しておきつつ他者の視点を吸収し、柔軟に最適解を探る姿勢が必要です。苦手な相手や別部署の人ほど新たな視点をもたらす可能性があると考え、積極的に意見を聞くとプロジェクトが加速します。
7. 古い計画やプライドを捨てる勇気
事業会社の現場は変化が激しく、一度作り上げた戦略やプランがすぐに通用しなくなる可能性も高いです。ここで大切なのは、執着し続けずに「あっさり捨てる」判断力。「時間かけたのにもったいない」という感情を脇に置き、組織と事業の利益を最優先に考えられるかどうかが試されます。
8. 目に見える成果を常に意識
事業会社では、論理の正しさより「ユーザーがどれだけ増えたか」「売上・利益がどう改善したか」などの数字のインパクトが評価基準になります。自分の施策がどのKPIにつながり、その結果どんな成果が出たのかを周囲に発信・共有し続けることで、組織内での信頼が高まり、追加予算やサポートを得やすくなるでしょう。

全体のまとめ
未経験からコンサル業界へ転職
コンサルティングファームは総じて中途採用を活発に行っており、未経験者でも高いポテンシャルが認められれば十分に転職できます。ただし、戦略ファームをはじめ倍率が高いファームほど、年齢・スキル・実績を厳しく見る傾向があります。さらに、ケース面接対策や志望動機の作りこみなど、しっかり準備をしておくことが転職しやすさを大きく左右します。若手のうちはポテンシャル採用が受けやすく、30代以降は即戦力としての期待値に応えられるかがカギになる点が特徴的です。
コンサルからコンサルへ転職
「今のファームで経験した分野とは別の案件に挑戦したい」「戦略系ファームでより短期成果を求める環境に身を置きたい」などの理由から、ファーム間の転職を希望する人も多いです。最適なタイミングはマネージャー昇進後がベストと言われるケースが多く、論点思考や戦略思考を使いこなせるよう現職で実績を積む期間が重要。いざ転職面接となると「マネージャークラスに求められる圧倒的なコンサル力」が試されるため、面接序盤からホームラン級の回答を打つ必要があります。
コンサルから事業会社へ転職
短期プロジェクトを短期間で切り盛りするコンサルから、同じ事業を長期視野で育てる事業会社へ移る例も増えています。自ら当事者として事業を動かす達成感を得られる反面、「給与や肩書きが下がる」「思った以上に社内調整が大変」などのギャップに悩むことも。ただし、コンサルで培った論理思考やPMOスキル、泥臭くでも結果を出す姿勢は大いに強みとなり、組織を巻き込むリーダーとして真価を発揮する場面が多いのも事業会社転職のメリットです。
戦略コンサルタントに転職しようかな?と思ったら
いかがでしたか?さいごに、戦略コンサルタントに転職をお考えの方にお役に立てる情報をまとめておきます。
戦略コンサルタントになるために必要な本を読んでみる
弊社代表のタカマツ本
コンサルティングファームに転職する際に特におすすめはフェルミ推定本!

戦略コンサルタントのための必読本
この世には、ケース面接対策本、コンサル思考、コンサル業界に関する本まで「コンサル」の関連本が山のようにあります。そこで、世の中に溢れる「これ、コンサル関連本?」と思われるタイトルの本を全て “購入し”、自ら読んで、
- 「ケース面接対策」という意味で、この本を読んだ本が良いかどうか?
- 読むのであれば、どのページを読めば良いのか?
を丁寧に解説しました。「どの本を読むべきなのか?」と迷われている方に、是非とも参考にして頂きたいです。

考えるエンジン講座無料相談で戦略コンサルを知る
戦略コンサルへの転職に必要な「考える力」を最も得意としているのが、私であり、年間500人以上が受講する「考えるエンジン講座」です。ので、是非とも、無料相談にいらしてください。
考えるエンジン無料相談はこちら
戦略コンサルタントの転職支援を251キャリアで
考える力を鍛え、戦略思考を身に付ける「考えるエンジン講座」の陰で隠れておりますが、じんわりと、コンサル向け転職エージェント=251CAREeR(ニコイチキャリア)もやっております。
ケース面接対策だけでなく、コンサルタントに強い転職エージェントも利用したい!という方は、是非とも、「無料相談」の時に、おしゃって頂ければと思います。

戦略コンサルタントの転職対策をテキストで学ぶ
フェルミ推定、ビジネスケース、志望動機など、コンサルタントへの転職の選考で実施される「ケース面接」対策に必要なオンライン教材を提供しています。