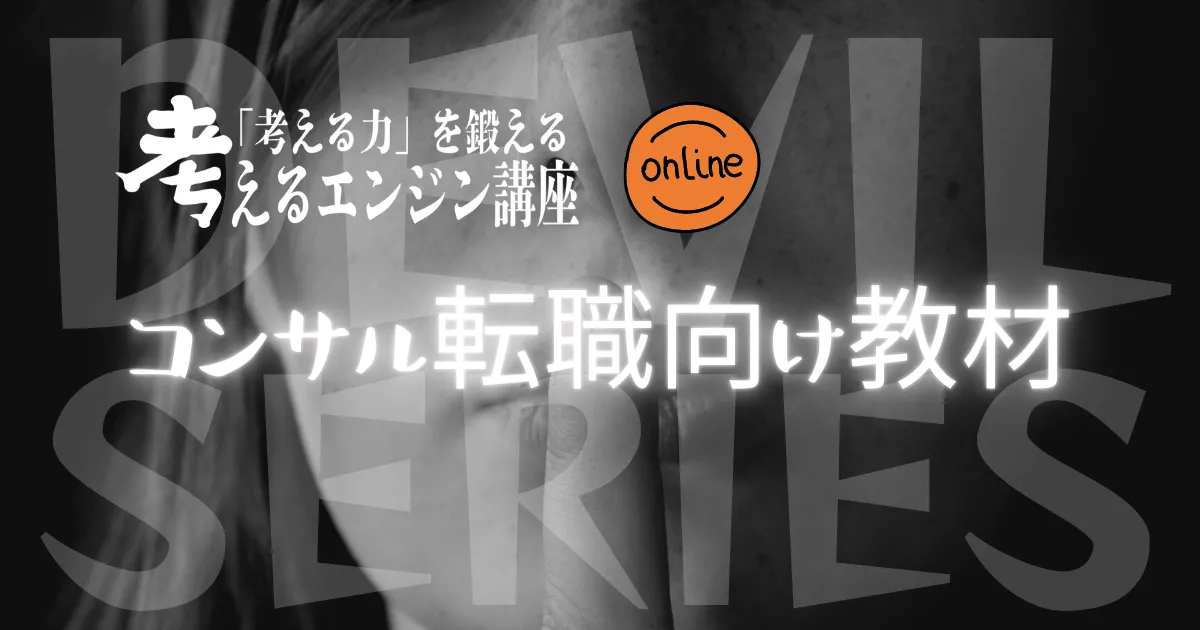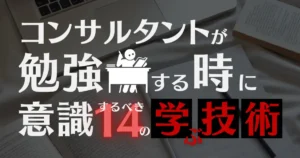コンサルタントが勉強する時に意識すべき14の『学ぶ技術』
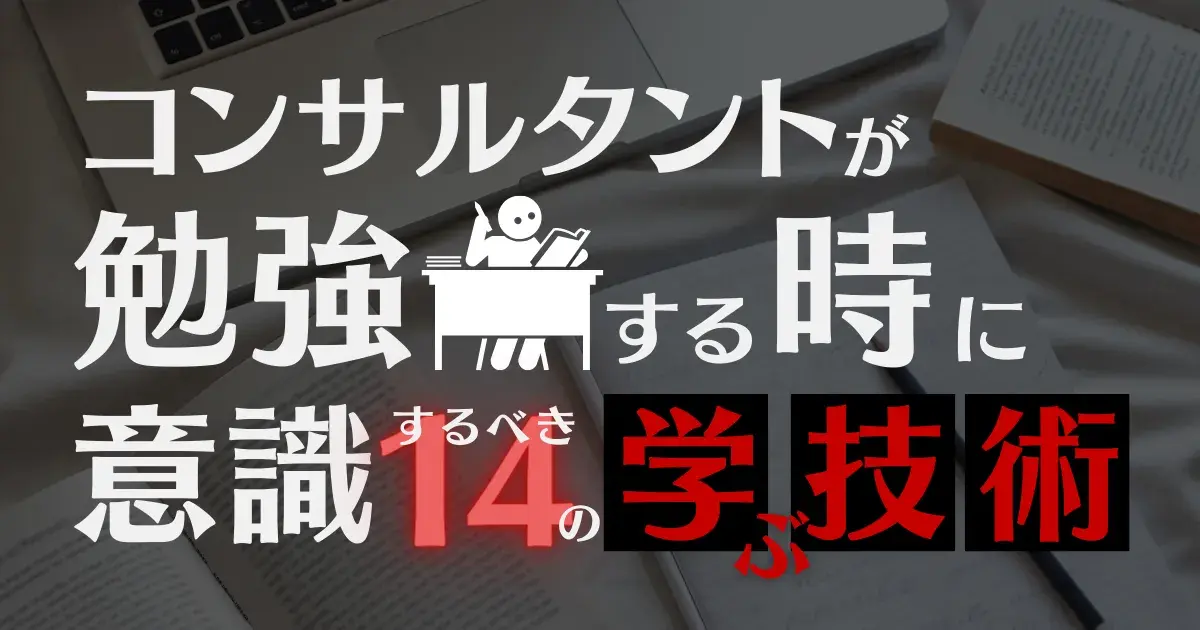
コンサルタントという職業は、クライアント企業の多様な課題を解決し、成果を出すために常に新しい知識やスキルを吸収しなければならない仕事です。ときには未知の分野に飛び込み、限られた時間でリサーチを行い、チームと協力しながら戦略を立案し、実行段階まで導いていく──そんな過程において、いかに学び続ける力を磨くかが、コンサルタントとしての成長を大きく左右します。
本記事では、勉強する際に押さえておきたい必須スキルや、効率的に学ぶための具体的なテクニックを紹介します。これからコンサル業界を目指す方だけでなく、すでに現役のコンサルタントとして働いている方にとっても、学びの姿勢や方法を見直す良いきっかけとなるはずです。さっそく、コンサルタントが勉強すべきスキルから見ていきましょう。
コンサルタントに求められるスキルセット
コンサルタントは多彩な分野の知識と実践的なスキルを身につけ、クライアントの経営課題を解決に導く役割を担います。ここでは、経営コンサルタントとして押さえておきたい主要な勉強分野と、その中でも特に重要なスキルを整理しました。
1. 国内外の経済動向と金融リテラシー
コンサルタントは世界的な出来事が企業経営に及ぼす影響を把握し、適切なアドバイスを行う必要があります。国内外の経済ニュースや金融政策、金利動向などを常にチェックし、自社やクライアントが直面するリスクと機会を見極めましょう。
- 最新の経済・金融知識
- リーマンショックやパンデミックなど突発的なリスクへの洞察
- 金融商品の仕組み、資本市場の動向などの理解
2. 法律に関する知識
法律は企業活動の土台となる重要な要素です。税制や雇用関連などの法律が変われば、経営方針にも大きな影響を与えます。コンサルタント自身も、法改正や新制度にアンテナを張り、クライアントにとって有益な情報をタイムリーに提示できるようにしておくことが不可欠です。
- 経営と深く結びつく法分野
- 税制(法人税、消費税、国際税務など)
- 労働法(雇用形態、労働時間、コンプライアンス)
3. IT・DXの知見
デジタル技術の活用が企業の競争力を左右する時代にあって、ITやDX(デジタルトランスフォーメーション)に関する知識は必須です。具体的なシステム導入や業務改善策を提案できると、コスト削減や業務効率化を実現し、クライアントからの信頼も高まります。
- IT活用の具体例
- クラウドサービス、AI・機械学習、IoTなどの導入支援
- データドリブンな経営判断のサポート
4. 語学力(英語など)
グローバル案件や外資系企業とのプロジェクトを担当する機会が増えているため、英語をはじめとする語学力は大きなアドバンテージになります。リサーチ資料やカンファレンスの内容は英語で提供されるケースが多いため、読解力とスピーキング力を身につけておくと重宝されるでしょう。
- 語学力強化のポイント
- ビジネス英語のボキャブラリーを磨く
- TOEICなどのスコアを活用して転職・昇進におけるアピール材料に
5. ロジカルシンキングとフレームワーク活用
問題解決において、論理的思考力は欠かせません。ロジックツリーやMECEといったフレームワークを使いこなし、情報の整理や論点の特定、適切なソリューションの立案を行います。
さらに、3C分析、PEST分析、SWOT分析などのフレームワークを使って市場や組織環境を多角的に捉えられるようになると、より説得力のあるコンサルティングが可能です。
6. 調査・分析スキル
経営戦略や業務改善の提案には、客観的なデータや事実に基づいた分析が不可欠です。マーケットリサーチやデータ分析の手法を習得しておくと、提案の精度が高まります。
- 具体的な分析手法
- 定量分析(統計データやシミュレーションの活用)
- 定性分析(インタビューやケーススタディなど)
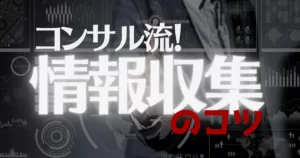
7. プロジェクト管理能力
複数のタスクを並行して進め、期限内に成果を出すためにはプロジェクト管理スキルが求められます。プロジェクトの計画立案や進捗管理、リソース配分をスムーズに行い、チームを適切に牽引することで、クライアントの満足度を高めることができます。
8. 各ジャンルの専門知識
コンサルタントとして大きな価値を提供するには、特定分野の専門知識を持っていると強みになります。例えば、製造業、金融、医療、ITなど、業界特化型の専門性を習得することで、より深い視点で課題解決に取り組めます。
9.コミュニケーションスキル
ロジカルシンキングを駆使して導いた結論も、クライアントやチームに正しく伝わらなければ意味がありません。相手の背景や立場を踏まえて、分かりやすく、かつ納得感を得られるコミュニケーションを行う力が求められます。特に、プレゼンテーションやファシリテーションの技術は、プロジェクトの成功に直結します。
10.クリエイティブシンキング
既存の枠組みにとらわれず、新しいビジネスモデルや革新的なソリューションを創出する思考力も、コンサルタントには必要です。デザイン思考やブレーンストーミングなどの手法を活用して、クライアント企業の潜在的なニーズや課題を掘り起こし、他社と差別化できる提案を生み出すことが重要となります。
コンサルタントが習得すべき14の「学ぶ技術」
「100%コピー」を目指す姿勢を忘れない
「100%コピー」を目指す姿勢を持つことは学びの第一歩です。指導者や上司のやり方が、自分と背景や経験値の異なる天才的なものであっても、あえて「すべて真似る」つもりで取り組んでみると、凡人ならではの壁や不足点が見えてきます。たとえば、格闘技の世界チャンピオンが使う技をそっくり真似しようとしても、全然同じ動きができないことに気づくでしょう。しかし、それでも100%を目指そうとする過程で、自分が本当に習得すべき核心部分が明確になり、結果的に学習効率が上がるのです。同様にコンサルの現場でも、美しく整理された先輩のスライドをそのまま再現しようとするときに、ポイントを掴む手がかりが自然と見えてきます。
まずはやってみる。背景や理由は後で尋ねる
学びの初期段階では、なぜそのやり方が正解なのかを逐一説明してもらうのは難しく、むしろ「まずは言われた通りにやってみる」ほうが早く成長できます。コンサルタントのマネージャーが「こう動いた方がいい」と言っても、その背景をすべて共有するわけではありません。できもしない段階で「なぜ?」を深く追求しても、教える側は十分に言語化しきれないことが多いものです。ひとまず言われた通りに実践し、手応えや違和感をつかんだ後に「どうしてこうなるんですか?」と尋ねれば、より深い意図を理解できます。
頭で分かったつもりにならない。言語化&行動して身につける
頭で理解しても、実際に行動しなければ本当の意味で身につきません。例えば、スポーツであれば新しい動きを動画や口頭の説明で「わかったつもり」になっても、実際に体を動かしてみると全然できない。同じくコンサルでいうと、資料作成やフレームワークの使い方を頭で理解しているだけでは不十分で、実際に白紙の状態から作ってみて初めて自分の理解度や欠点が見えてきます。言語化してノートに書いたり、誰かに説明するなど、行動とアウトプットをセットにすることが学習定着の鍵になります。
人は驚くほど忘れる。物理的に貼りだして可視化
人間は想像以上に物事を忘れやすい存在であり、特に新しい知識はあっという間に抜け落ちます。東大出身の優秀なコンサルタントでも、PCのデスク周りにメモや付箋をたくさん貼る光景は珍しくありません。優秀な人ほど自分の忘却力を自覚しているからこそ、わざわざ紙に印刷して見えるところに置くわけです。これは勉強した内容を「目に触れる場所」に物理的に貼り付けるなどの工夫をするだけで、学習したスキルをより長く頭の中にとどめておく効果があります。
続かないのが当たり前。三日坊主対策を最初から仕込む
「三日坊主になってしまうのは当たり前だ」という前提で学習環境を整えるのは非常に重要です。多くの人はモチベーションが続くと思い込んでスタートし、結局あっさり投げ出してしまいます。例えば、剣道や柔道の道場では、仲間を作り「通うこと自体が楽しくなる仕組み」を用意することで継続率が上がります。ビジネスの勉強でも、誰かと一緒にスケジュールを立てて毎週進捗を報告するといった、意志力以外の仕組みによって自分を律する方法を採れば途中でやめにくくなるものです。
学習を邪魔する「水差し」を遠ざける
学びを始めたタイミングで「どうせ無駄だよ」「才能ないんじゃない?」と冷水を浴びせられると、一気にモチベーションを失うことがあります。初期段階ほど小さな否定意見に心が折れやすいため、学習初期はそういう環境や人からできるだけ離れておくことが大切です。たとえば、読書習慣を身につけようとしている時に、本の価値を否定する人と話してしまうと、せっかくの意欲が削がれてしまうかもしれません。学ぶときには周囲の雰囲気や関わる人にも気を配り、ネガティブな影響を最小化するように設計すると成果が出やすいのです。
成長を実感できる仕組みを取り入れる
継続には「成長を実感できる仕組み」が欠かせません。柔道の帯の色が変わるのが嬉しいのは、自分の努力が形になってわかりやすいからです。同様にビジネスでは、定期的に模擬試験やケーススタディにチャレンジしてスコアを見える化する、ミニコンペで評価を受けるなど、客観的な指標で進歩を確認できる仕組みを作るとやる気が持続します。人はどれだけ素晴らしい理屈を並べられても、自分で「できるようになった!」と感じないと本気で続けにくいものです。
コミュニティ化・仕組み化で学習を加速
学習を加速させるためには、一人で黙々とやるよりもコミュニティに参加したり、仲間と切磋琢磨し合うと効果的です。弊社が提供してる「考えるエンジン」などのグループに属しておけば、各自の学びを持ち寄って刺激し合うチャンスが増えます。組織内で同じスキル向上を目指すメンバーと勉強会を開いたり、オンラインコミュニティで情報交換したりするだけで、モチベーションも吸収率も向上するものです。
質問力を鍛えて吸収力をアップ
吸収力を高めるうえで「質問の質」は非常に大きな役割を持ちます。コンサル上司や師匠に「わからないんですけど……」と投げるのではなく、まずは自分で一度考えてみたうえで「ここまでは理解しましたが、この部分が腑に落ちません」と問いかける方が、相手も教えやすいし回答も的確になります。さらに「これって具体的な事例でいうと、〇〇企業のケースみたいな感じですか?」と具体的に聞くと、抽象論ではなく実際に使える知見が返ってきやすいのです。こうした質問力を磨けば、ただ聞き流すだけよりもはるかに効率的にノウハウを得られます。
定期的にテストや評価の場をつくる
自分がどの程度身につけられているのかを確かめる「テストや評価の機会」を定期的に設けるのも重要です。ボクシングならスパーリングや試合がその役割を果たしますし、ビジネスの場合はプレゼンコンペや資格試験、ケーススタディ発表などが該当します。客観的に結果を測られると、弱点が明確になり、その後の学習方針も立てやすくなります。試験や評価で不甲斐ない結果が出たとしても、そこからやり方を修正して再挑戦できるのが学びの醍醐味です。
異なる分野や複数のコミュニティを掛け合わせる
学びをより深めるために異なる分野やコミュニティを掛け合わせるのも効果的です。例えば、コンサル思考と格闘技や武道の身体感覚が組み合わさると、論理だけではわからない「実践から得る気づき」があり、思わぬアイデアが生まれやすくなることもあります。ITとマーケティングを掛け合わせたり、金融業界と人材育成の知識をミックスしたりするように、まったく別の領域との接点を作ることで視野が広がり、創造性も高まるのです。
習得した技術も常にアップデート
習得したと思っているスキルも、時代や環境が変わればアップデートが必要です。フレームワークやテクニックも一度学んで終わりにするのではなく、常に新しい情報や応用事例をキャッチアップし、自分のやり方を最新の状態に保ちましょう。フレームワークも、追加要素を加えたり細分化したりするバージョンが次々生まれていますから、定期的に学び直しをする姿勢こそがコンサルタントの武器になります。
ネタ帳・アイデア帳を常に持ち歩く
学んだことや思いついたアイデアはすぐに忘れてしまうので、手元にネタ帳やメモアプリを常に用意しておくと便利です。講義を受けたり、新しい技を見たりした瞬間に「こういう使い方ができそう」とイメージが浮かんだら、その場で書き留めるだけで定着度は大きく変わります。あとになって振り返ると、当時の気づきを再度掘り下げる材料にもなるので、「思いついた時にすぐ書く」姿勢を徹底するのがおすすめです。
参考図書を活用し、「学ぶこと」自体を学ぶ
最後に、「学ぶ」そのものについて考察した書籍を活用するのも大切です。コンサルタントとして知識を吸収するだけでなく、「達人はどういうプロセスで学習するのか」「わかるとは何なのか」といったテーマを深堀りした『達人のサイエンス』や『畑村式わかる技術』のような本を読むと、自分の学習スタイルを客観的に見直すヒントを得られます。どんなに優れたコンサルであっても常に学ぶことが仕事の本質。そうしたメタ視点を持つことで、学習効率はさらに上がるでしょう。

コンサルタントの世界は知識や手法が瞬く間にアップデートされていきますが、それに追いつくには単にインプットを増やすだけでなく、行動によるアウトプットを通じて「わかった」と「できる」をつなげる工夫が欠かせません。ここで紹介した14の学ぶ技術を意識して取り組めば、新しいスキルが身につくだけでなく、その過程すら楽しめるようになるはずです。小さな挑戦を積み重ね、継続的に自己成長していく姿勢こそが、優れたコンサルタントの礎となります。
コンサル転職に限らず、学び続けるマインドセットを持つ
コンサルタントという仕事は、企業の経営課題や組織改革、戦略立案など、多岐にわたる領域で「最適な解決策」を提供する役割です。常に最先端の知識や手法を求められるため、入社前・転職前にどれだけ準備をしていても、入社後・転職後における学びは不可欠です。むしろ、現場に立った後こそが本当のスタートラインであり、そこでの勉強や自己研鑽が、あなたのコンサルタントとしての成長や市場価値を大きく左右します。
学び続けるマインドセットは「コンサルタントの宿命」
コンサルティングファームに入るまでにロジカルシンキングやフレームワークをしっかり身につけても、実際のプロジェクトでは業界特有の知識や新しいITツール、顧客企業ごとの文化や課題に合わせた対応力が求められます。
- 入社前の学習:ロジックツリーやMECEなど、基礎的なコンサルスキルを習得しておく
- 入社後・現場での学習:実際のクライアント案件で立ちはだかる想定外の課題に対処するため、業界の動向やテクノロジー、内部統制の仕組みなどを新たにキャッチアップする
これらのギャップを埋めるには、常に新しい知識を吸収しようとする姿勢が欠かせません。
転職後こそさらに深まる学びのステージ
転職して別のコンサルティングファームに移ったり、異なる業界・専門領域に挑戦すると、学ぶべき範囲は再び広がります。特に総合系から戦略系、あるいは専門特化型ファームへの転職では、扱う課題の次元やディスカッションの深さが大きく変わってくる場合があります。
- 戦略系ファームへの転職:経営の最上流でトップマネジメントとやり取りするため、高度な戦略立案のノウハウやファシリテーションスキルが求められる
- IT特化のコンサル企業への転職:システム導入やDX推進に精通する必要があり、テクノロジー関連の勉強は必須
転職を機に環境やクライアントが変わるほど、身につける知識やスキルはアップデートを余儀なくされます。言い換えれば、転職をするたびに新しい学習機会が生まれるということでもあります。
職種や業界に関わらず大切な「学びの姿勢」
学び続けるマインドセットは、コンサルティング業界に限らず、あらゆる業種・職種で活きる普遍的な姿勢でもあります。技術革新やマーケットの変化が激しい現代では、「一度学んだからもう大丈夫」という考え方は通用しません。
- IT業界:プログラミング言語やクラウドサービスは日進月歩で進化
- 金融業界:新たな商品や規制、世界経済の動向に常に敏感である必要がある
- 製造業:グローバルサプライチェーンやSDGsへの取り組みなど、新トレンドをいち早く取り入れる姿勢が求められる
このように、どの業界でも「新しい知識を貪欲に吸収し、変化に合わせて行動を修正する」能力がある人材は重宝されます。
学び続ける人が「次のステージ」へ進んでいく
コンサルタントとして働くうえで、あるいは他の職種でも同様に、学びに終わりはありません。入社前・転職前の準備やスキルアップがゴールなのではなく、現場に立ったその日から再び学習のサイクルが回り始めます。
- 現場で初めて見えるリアルな課題やプロジェクトの進め方
- 新しいファームやポジションで体感する、まったく異なる常識や専門知識
- 時代の変化に対応するために常に必要となる自己研鑽
これらすべてを通じて、あなたは確実にキャリアを高め、より高度なステージへとステップアップしていくでしょう。学び続ける姿勢こそが、コンサルタントの成長と成功を永続的に支える最大のエンジンなのです。
戦略コンサルタントに転職しようかな?と思ったら
いかがでしたか?さいごに、戦略コンサルタントに転職をお考えの方にお役に立てる情報をまとめておきます。
戦略コンサルタントになるために必要な本を読んでみる
弊社代表のタカマツ本
コンサルティングファームに転職する際に特におすすめはフェルミ推定本!

戦略コンサルタントのための必読本
この世には、ケース面接対策本、コンサル思考、コンサル業界に関する本まで「コンサル」の関連本が山のようにあります。そこで、世の中に溢れる「これ、コンサル関連本?」と思われるタイトルの本を全て “購入し”、自ら読んで、
- 「ケース面接対策」という意味で、この本を読んだ本が良いかどうか?
- 読むのであれば、どのページを読めば良いのか?
を丁寧に解説しました。「どの本を読むべきなのか?」と迷われている方に、是非とも参考にして頂きたいです。

考えるエンジン講座無料相談で戦略コンサルを知る
戦略コンサルへの転職に必要な「考える力」を最も得意としているのが、私であり、年間500人以上が受講する「考えるエンジン講座」です。ので、是非とも、無料相談にいらしてください。
考えるエンジン無料相談はこちら
戦略コンサルタントの転職支援を251キャリアで
考える力を鍛え、戦略思考を身に付ける「考えるエンジン講座」の陰で隠れておりますが、じんわりと、コンサル向け転職エージェント=251CAREeR(ニコイチキャリア)もやっております。
ケース面接対策だけでなく、コンサルタントに強い転職エージェントも利用したい!という方は、是非とも、「無料相談」の時に、おしゃって頂ければと思います。

戦略コンサルタントの転職対策をテキストで学ぶ
フェルミ推定、ビジネスケース、志望動機など、コンサルタントへの転職の選考で実施される「ケース面接」対策に必要なオンライン教材を提供しています。