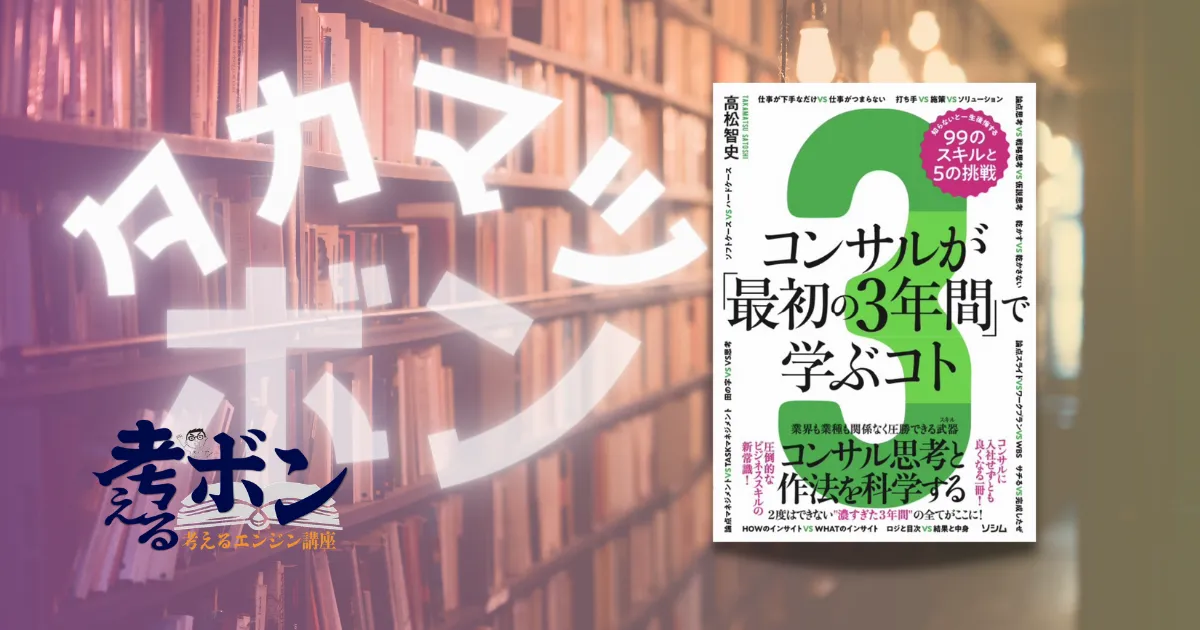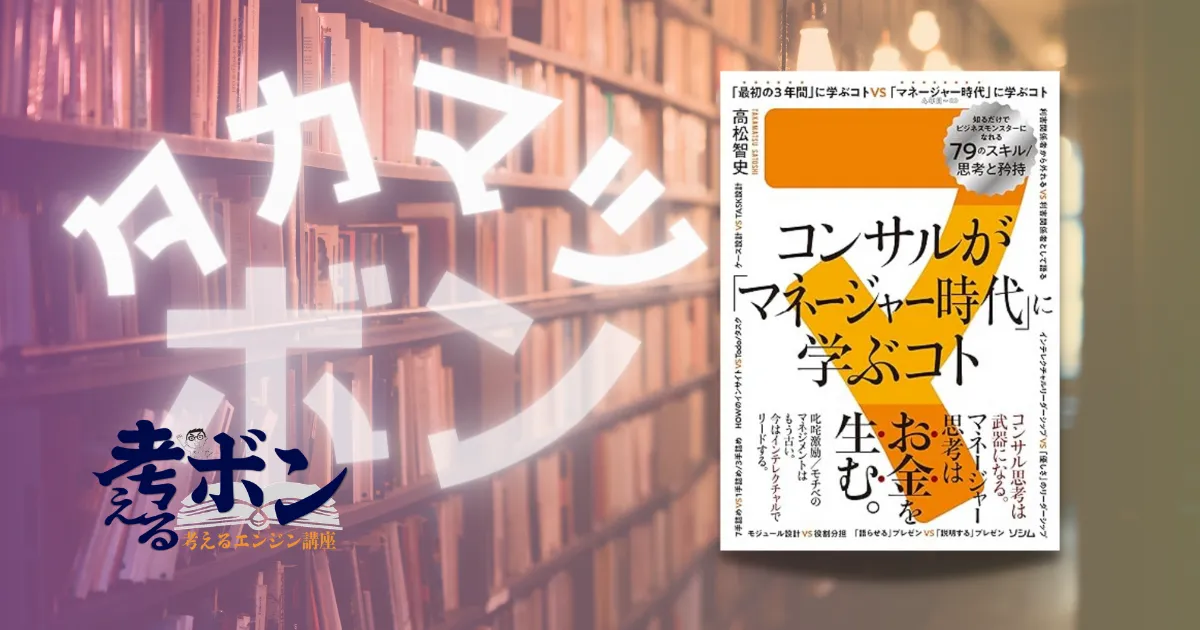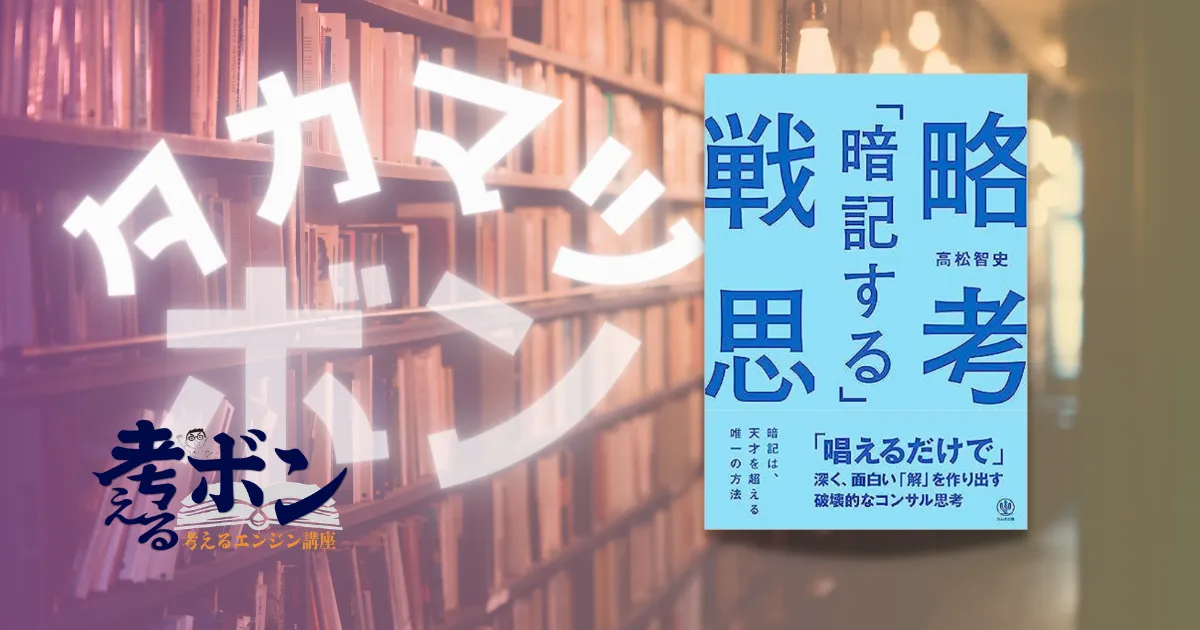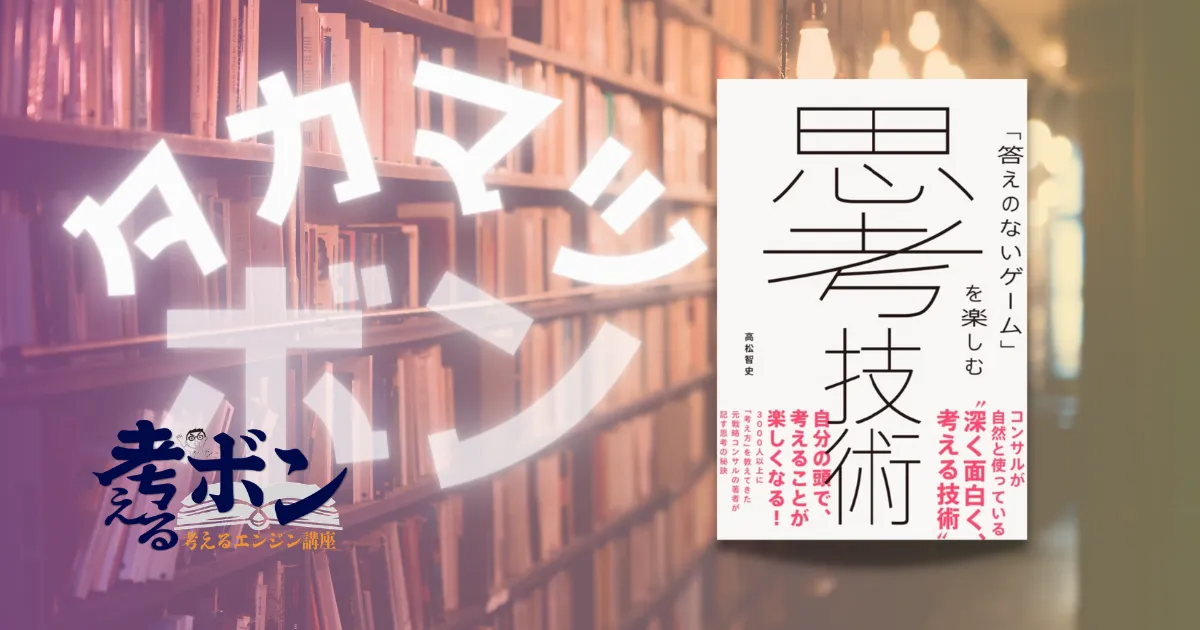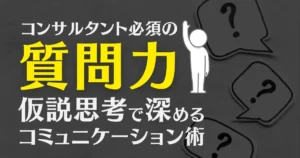コンサルタント必須の質問力!仮説思考で深めるコミュニケーション術
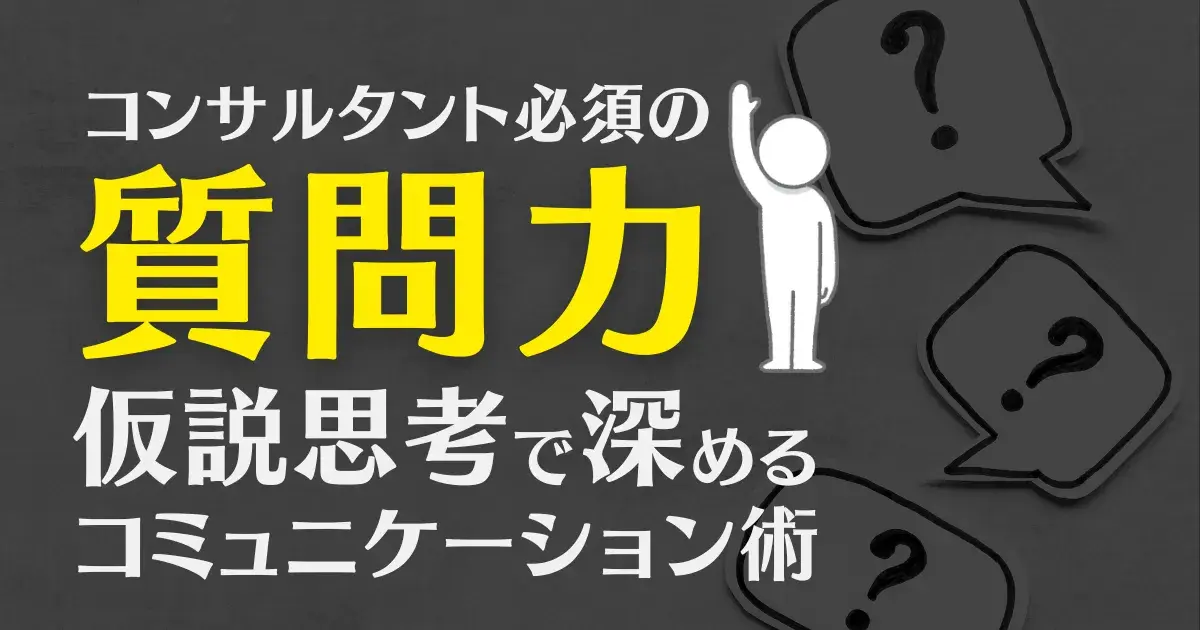
コンサルティングの現場で成果を出すためには、仮説を立てて検証し、短時間で答えを導く思考力が欠かせません。そして、その思考力を支える基盤ともいえるのが「質問力」です。
何をどう聞けば、問題の真因に近づけるのか。上司やクライアントから的確な回答を得てプロジェクトをスムーズに進めるには、ただ「わかりません」と投げかけるのではなく、仮説や目的を持った質問をすることが大切です。
本記事では、コンサルタントがなぜ質問力を重視するのかを解説するとともに、オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンの違いや、質問力を磨くための具体的なポイント、さらに上司への質問テクニックまでを体系的に紹介します。「答えを知る」だけでなく「相手から知りたい情報を上手に引き出せるコンサルタント」を目指したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
質問の種類
コンサルの現場でよく使われる質問には、大きく分けて「オープンクエッション」と「クローズドクエッション」の2種類があります。どちらも使い方次第で得られる情報やコミュニケーションの質が変わってくるため、違いを正しく理解して使い分けることが重要です。
オープンクエッション
オープンクエッションは、相手が自由に答えられるように問いかける方法です。たとえば「この施策を検討するうえで、どんな課題があると感じていますか?」のように、回答の選択肢をあえて広げることで、相手の考えや意見を幅広く引き出す効果があります。コンサルタントが深い洞察を得たいときや、相手の優先順位や重視するポイントを探りたいときに適しています。
メリット
- 相手が話しやすい
回答者が自分の言葉で自由に意見を述べられるため、会話が活発になりやすい。 - 潜在的な課題や価値観を発見できる
準備された選択肢がない分、回答者が重要視している視点や想定外の問題点が浮き彫りになることがある。 - 親身な印象を与えやすい
自由な回答を受け止める姿勢を示すことで、クライアントやチームメンバーに「よく話を聞いてもらえている」という安心感を与える。
デメリット
- 情報が散逸しがち
答える範囲が広すぎる場合、要点がバラバラになってしまい、整理に時間がかかる。 - 回答者の前提が共有されにくい
相手が当然と思っている知識や背景情報は省かれてしまう可能性があり、重要な事実が埋もれるリスクがある。
質問例
- 「今回のプロジェクトで感じている課題を教えていただけますか?」
- 「この戦略案について、どのような懸念点がありますか?」
- 「今後の方向性について、率直にどう考えていますか?」
活用のコツ
- 5W1Hを適度に使う
完全に自由に答えさせると戸惑わせることもあるため、「どのエリアで」「いつまでに」など、ある程度答えの範囲を示すとスムーズに意見を引き出せる。 - ポイントを要約・確認しながら進める
情報が散らばらないよう、相手の話を途中でまとめ、理解のズレがないか確認する。
クローズドクエッション
クローズドクエッションは、「はい/いいえ」や「A/B/C」など、回答の選択肢をあらかじめ限定する質問方法です。たとえば「今回の提案Aに賛成ですか? 反対ですか?」のように、相手から明確な回答を得る際に効果的です。仮説検証型のアプローチを取るコンサルタントにとっては、情報整理や議論の方向性を固める際に役立ちます。
メリット
- 回答が具体的で整理しやすい
選択肢を設定するため、得られる情報にブレが少なく、結論をまとめるのがスピーディー。 - 仮説検証に向いている
自分が立てた仮説に対し、「イエス・ノー」や「A・B」などで答えてもらうことで、迅速に要点を確かめられる。 - 回答者が答えやすい
質問が短く明確なので、迷わず答えられる場合が多い。
デメリット
- 回答者が誘導されていると感じることがある
提示した選択肢の中に相手の本音がない場合、重要な情報を取りこぼすリスクがある。 - 仮説が間違っていると軌道修正が難しい
限定的な質問に固執すると、本来の問題の根幹を見落とす可能性がある。
質問例
- 「こちらの予算案でよろしいですか、それとも別の案を検討しますか?」
- 「今回の会議で決めるべき優先順位は、この2点でよいでしょうか?」
- 「新製品のターゲットはA社と同じセグメントで問題ないですか?」
活用のコツ
- 仮説を明確にしておく
どんな回答がほしいのか、事前にゴールを設定しておく。仮説を検証する質問であるほど、効果的に議論を絞れる。 - オープンクエッションと組み合わせる
クローズドクエッションのみでは相手の意見を狭めてしまうため、広く意見を引き出したいときは先にオープンで聞き、最後にクローズドで絞り込む流れが望ましい。
コンサルで質問力が大事な理由
コンサルティングの現場では、常に「考える」ことが求められます。中でも“質問を作る”という行為自体が、一つの思考プロセスを踏むうえで非常に効果的です。たとえば、漠然と「わかりません」と尋ねるのではなく、「○○という理解で合っていますか?」と仮説を立てたうえで質問することで、わからない部分を具体的に示すだけでなく、自分の考えを整理して思考を深めることができます。以下では、コンサルの現場で質問力が重視される理由を解説します。
1. 質問を組み立てる過程が思考力を鍛える
コンサルタントは問題に対して常に仮説を持ち、短時間で検証と修正を繰り返すことが重要です。質問をする際に「こういう前提でこう考えた結果、ここがわからない」という形を取れば、自然と自分の中で思考が1回転します。
- 仮説を立てる→質問を作る→回答を得る→仮説を検証する
この一連のプロセスを踏むたびに、論点が明確になり、結果として思考が深まっていくのです。
2. 質問が上司やクライアントに「考えている」ことを伝える
コンサルティングの仕事では、上司やマネージャーとのやり取りが頻繁に行われます。ただ指示を受けるだけで「何がわかりません」と聞き返すのでは、相手から「自分で考えていない」と見られがちです。一方、クローズドクエスチョンを使って仮説を提示しながら質問すれば、上司に「ちゃんと考えて行動している」という印象を与えられます。
- 悪い質問例:「全然わからないんですが、どうすればいいでしょうか?」
- 良い質問例:「○○という意図で進めた結果、△△で詰まっています。□□という理解で大丈夫でしょうか?」
この違いによって、上司の信頼度や次のフィードバックの質が大きく変わるのです。
3. 「わからないこと」を明確化し、効率的なコミュニケーションができる
「オープンクエスチョン」も有用な場面はありますが、コンサルタントは仕事を迅速に進めるうえで、ある程度対象を絞った問いかけをする場面が多いです。仮説を前提に相手とコミュニケーションを取れば、相手も「どこをどう補足すればいいか」がわかりやすくなり、短時間で要点に絞ったやりとりが実現します。
逆に、「よくわからないので全部教えてください」というオープンクエスチョンだけでは、相手の方も回答に困り、必要な情報が得られないまま時間が過ぎてしまうかもしれません。
4. マネージャーからの評価やサポートにつながる
コンサルティング会社では、上司やマネージャーがプロジェクトメンバーにタスクを任せるたび、「自分でやった方が早いし質も高い」というジレンマを抱えることがあります。そのなかでメンバーが仮説を持った質問を投げかけてくれれば、マネージャーは「この人はきちんと考えている」「成長させがいがある」と感じ、積極的にノウハウを教えたりフォローしてくれるようになります。結果的に、メンバー自身もコンサルタントとして早くステップアップできるのです。
質問力を磨くために意識すべきこと
コンサルタントとしての質問力を高めるためには、「わからないことを素直に質問する」だけではなく、自分なりの仮説や目的を持ったうえで問いかける姿勢が不可欠です。ここでは、質問力を高めるための3つのポイントに焦点を当てて解説します。
1. 無駄なプライドを捨てる
コンサルティングファームに入社する人は、幼い頃から勉強で好成績を収め、一流大学を卒業してきた優秀な人材が多いでしょう。ところが、彼らですらファームに入社して初めて体験するプロジェクトや業界特有の言葉・手法を前にすると、何が起きているのかわからなくなることがあります。
そこで邪魔をするのが「優秀でありたい」というプライドです。
- 「ここでバカな質問をしたら、周りにどう思われるんだろう…」
- 「こんな初歩的なこと聞いてもいいのかな…」
こうした遠慮は、学びのチャンスをつぶしてしまいがちです。実際には、入社したばかりの環境でわからないことが出てくるのは当然のこと。むしろ、わからないことをきちんと言語化して周囲に質問できる勇気が、その後の成長スピードを左右します。まずは無駄なプライドを捨て、素直に疑問を口にする心構えを持ちましょう。
2. 質問には仮説をつける
質問をする際に、ただ「よくわかりません」「詳細を教えてください」と漠然と投げかけると、相手はどこから説明すればいいのかわからず、双方にとって非効率になりがちです。そこで役立つのが、質問に仮説を付けるというアプローチです。
- 悪い例:「プロジェクトの目的がわかりません。どういうことですか?」
- 良い例:「プロジェクトの目的はA領域の売上向上、もしくはBサービスの立ち上げ支援だと理解しているのですが、正しいでしょうか?」
後者のように「○○だと理解しています。合っていますか?」と仮説を提示したうえで質問をすると、相手も的確に「そこは合っている」「ここは違う」と返答してくれます。結果として会話の生産性が高まり、自分の思考も一段深まるメリットがあるのです。また、仮説が外れていても問題ありません。外れるほど「何が正解で何が違うのか」がクリアになるため、成長のきっかけになります。
3. 自分の行動が変わる質問を考える
質問するたびに、自分の行動や判断が具体的に変わるような問いを考えることも重要です。
たとえば、上司から急ぎの依頼を受けた時に「これはいつ使う資料ですか?」と聞くことで、「すぐ対応すべき」か「後回しでも大丈夫」かが判断できます。あるいは、キャリアに関する質問をする際に、「これがAなら受講する、Bならまだ受講しない」というように、自分の行動を決定づける前提で仮説を立てておくと、質問の質が自然と高まります。
この「行動が変わる質問」という観点を常に持つと、情報を得るだけで終わらず、得た情報をもとに具体的な次のステップへ移行できるようになります。例えば、
- 「この資料を来週使うなら今日終わらせますが、再来週以降なら別のタスクを優先してもいいでしょうか?」
- 「この研修で学べる内容が○○だったら受講を検討しますが、△△なら別の研修を検討してもいいですか?」
このように質問と行動をセットにすると、質問力だけでなく、意思決定力や段取り力も飛躍的に向上するのです。
上司に「正しい質問」をするには?
これまで「オープンクエスチョンはNG」のような流れで解説してきましたが、実際の現場ではオープンクエスチョンが必要となるケースも少なくありません。ただし、上司に質問する場合は、単に「わからないことをぶつける」のではなく、自分の理解度や疑問点をしっかり整理したうえで問いかけることが肝心です。ここでは、上司の時間を無駄にしないためのポイントと、「あえてオープンクエスチョンが必要なときにも、どのように工夫すればよいか」についてまとめます。
1. 「わからない」ではなく「何がわからないか」を整理する
コンサルタントにとって時間は貴重なリソース。上司もその価値を十分理解しています。単に「よくわかりません」と言うだけでは、上司から「何がわからないの?」と逆に質問され、双方の時間が浪費される可能性があります。
そこで大切なのは、自分がどこまで理解できていて、どこがわかっていないのかを明確にすること。事前にGoogleなどで調べて解決できることは自分で解決し、どうしても理解できない部分だけをピックアップするようにしましょう。
- 悪い質問例:「人事制度策定について、何をするのか全然わからないんですが……」
- 良い質問例:「人事制度策定の流れは理解できたのですが、先方のキーマン構成と合意形成プロセスがまだ把握しきれていません。そこを教えていただければ理解が深まると思います」
こう伝えれば、上司も具体的なアドバイスがしやすくなるだけでなく、「自分で考えて努力したうえで質問している」という前向きな姿勢が伝わります。
2. 「これがわかれば全体像を把握できる」というゴールを示す
上司に質問するときは、「ここがわかれば、プロジェクト全体を理解できます」というゴールを先に示すと効果的です。上司は常に、「チームメンバーが効率的に仕事を理解し、成果を出すにはどうすればよいか?」を考えています。
- 具体的な例「○○さん、先ほどのミーティングがよく理解できなくて…時間をいただけますか?
僕の中では、(1)先方の人間関係の把握、(2)今回検討している具体的な施策、(3)その施策における課題の3点を押さえられれば、おおよその流れがつかめると思っています」
このように質問前の整理ができていると、上司としては「ここを説明すればいいんだな」と把握しやすく、回答がスムーズになります。さらに「考えているな」と好印象を持ってもらいやすいのも大きなメリットです。
3. あえてオープンクエスチョンを使うなら「フレームの提示」を
上司への質問では仮説を立てたクローズドクエスチョンが基本ですが、場合によってはオープンクエスチョンで広く情報を得たいこともあるでしょう。そんなときは、答えやすい形になるようある程度のフレームを提示してオープンにするのがおすすめです。
- フレームを提示したオープンクエスチョンの例「○○さん、今回のプロジェクトで課題になりそうな点は、組織面・システム面・予算面だと思うのですが、他に見落としている要素はありますか?」
まったく自由な「オープンクエスチョン」を投げると、上司も回答に困ることがあります。一方、あらかじめ思考の枠組みを提示してから「他に抜け漏れがあるか」を問うことで、上司はさらに補足しやすくなります。
4. 上司は「質問大歓迎」だと知っておく
コンサルタントの上司やマネージャーにとって、部下やジュニアコンサルからの質問は、大きなメリットがあります。なぜなら、
- メンバーの理解度や進捗を正しく把握できる
- 思いがけない視点やインサイトを得られる可能性がある
- コミュニケーションを深める機会になる
部下がどこにつまずいているのか、どのような見解を持っているのかは、上司にとって“調べてわかる”情報ではありません。適切な質問は、プロジェクトをスムーズに進めるうえでも重要なインプットとなります。そのため、「質問していいのかな…」と遠慮する必要はありません。ただし、前述のように最低限の整理や仮説立案は必須です。
戦略コンサルタントに転職しようかな?と思ったら
いかがでしたか?さいごに、戦略コンサルタントに転職をお考えの方にお役に立てる情報をまとめておきます。
戦略コンサルタントになるために必要な本を読んでみる
弊社代表のタカマツ本
コンサルティングファームに転職する際に特におすすめはフェルミ推定本!

戦略コンサルタントのための必読本
この世には、ケース面接対策本、コンサル思考、コンサル業界に関する本まで「コンサル」の関連本が山のようにあります。そこで、世の中に溢れる「これ、コンサル関連本?」と思われるタイトルの本を全て “購入し”、自ら読んで、
- 「ケース面接対策」という意味で、この本を読んだ本が良いかどうか?
- 読むのであれば、どのページを読めば良いのか?
を丁寧に解説しました。「どの本を読むべきなのか?」と迷われている方に、是非とも参考にして頂きたいです。

考えるエンジン講座無料相談で戦略コンサルを知る
戦略コンサルへの転職に必要な「考える力」を最も得意としているのが、私であり、年間500人以上が受講する「考えるエンジン講座」です。ので、是非とも、無料相談にいらしてください。
考えるエンジン無料相談はこちら
戦略コンサルタントの転職支援を251キャリアで
考える力を鍛え、戦略思考を身に付ける「考えるエンジン講座」の陰で隠れておりますが、じんわりと、コンサル向け転職エージェント=251CAREeR(ニコイチキャリア)もやっております。
ケース面接対策だけでなく、コンサルタントに強い転職エージェントも利用したい!という方は、是非とも、「無料相談」の時に、おしゃって頂ければと思います。

戦略コンサルタントの転職対策をテキストで学ぶ
フェルミ推定、ビジネスケース、志望動機など、コンサルタントへの転職の選考で実施される「ケース面接」対策に必要なオンライン教材を提供しています。
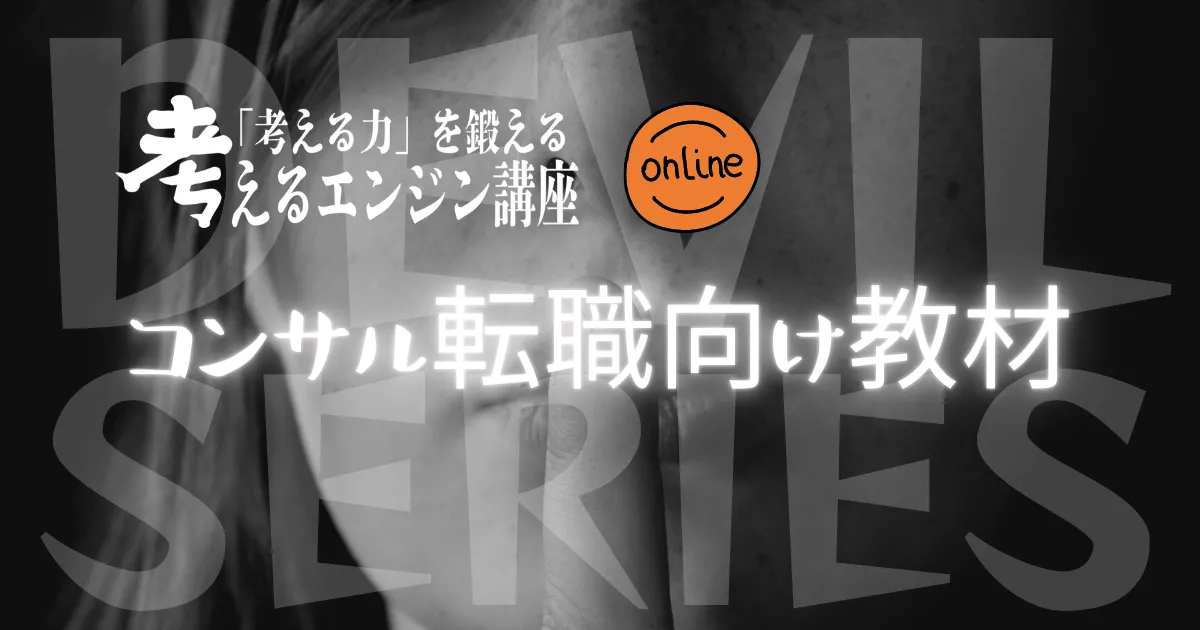
戦略コンサルタントの転職対策を動画で学ぶ
コンサルが「最初の3年間」で学ぶコト
「戦略思考」 =「解、答え、意見、メッセージ」を作り出す考える技術を、「暗記する」=「考える際に自分に問う、声に出して唱える」フレーズを覚えるだけで身につけられる 「思考技術」の本です。
コンサルが「マネージャー時代」に学ぶコト
10万部を超えた『コンサルが「最初の3年間」で学ぶコト』の続編であり完結編にして、過去最高傑作。400ページにもわたる至高の “熱き講義形式” ボン。
コンサルタントが『マネージャー時代』に学ぶコト、学ぶべきことを詰め込んでおります。
「暗記する」戦略思考
「戦略思考」 =「解、答え、意見、メッセージ」を作り出す考える技術を、「暗記する」=「考える際に自分に問う、声に出して唱える」フレーズを覚えるだけで身につけられる 「思考技術」の本です。
「答えのないゲーム」を楽しむ思考技術
限られた情報からどのようなプロセスでいい示唆や仮説を導き出すか?本書ですべて解説します。「思考って、技術=スキル、後天的に身に着けられるんだ!」って、確信できるはず。この1冊で「考えること」が楽しくなる!