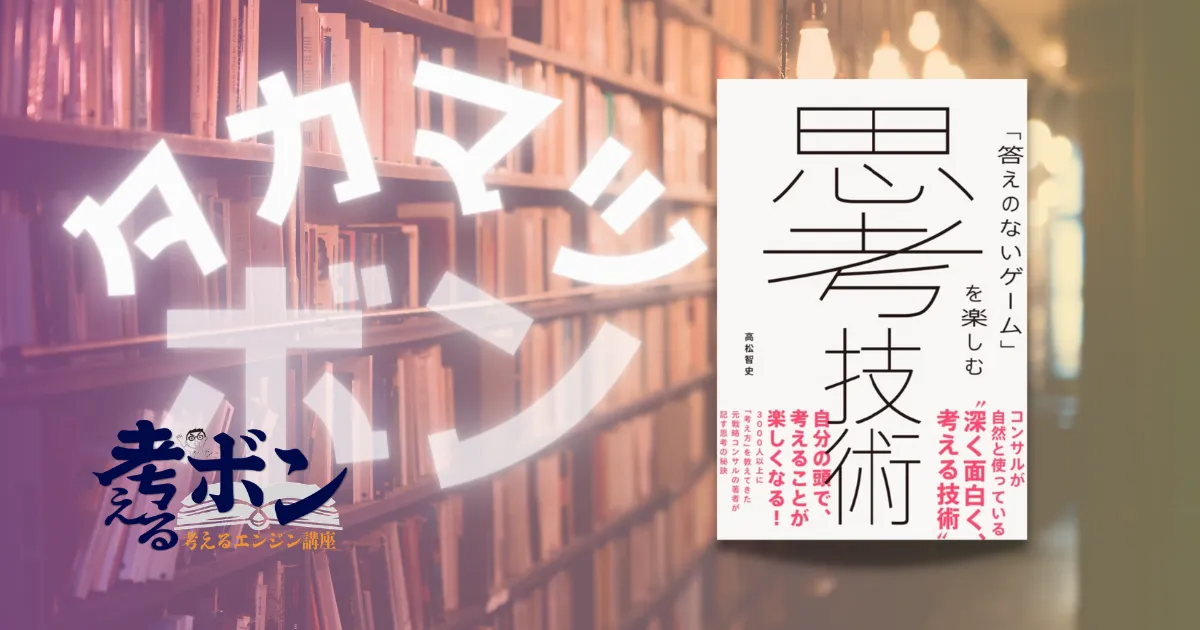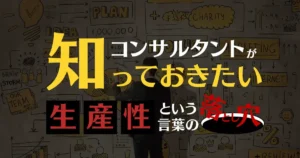コンサルタントが知っておきたい「生産性」という言葉の落とし穴
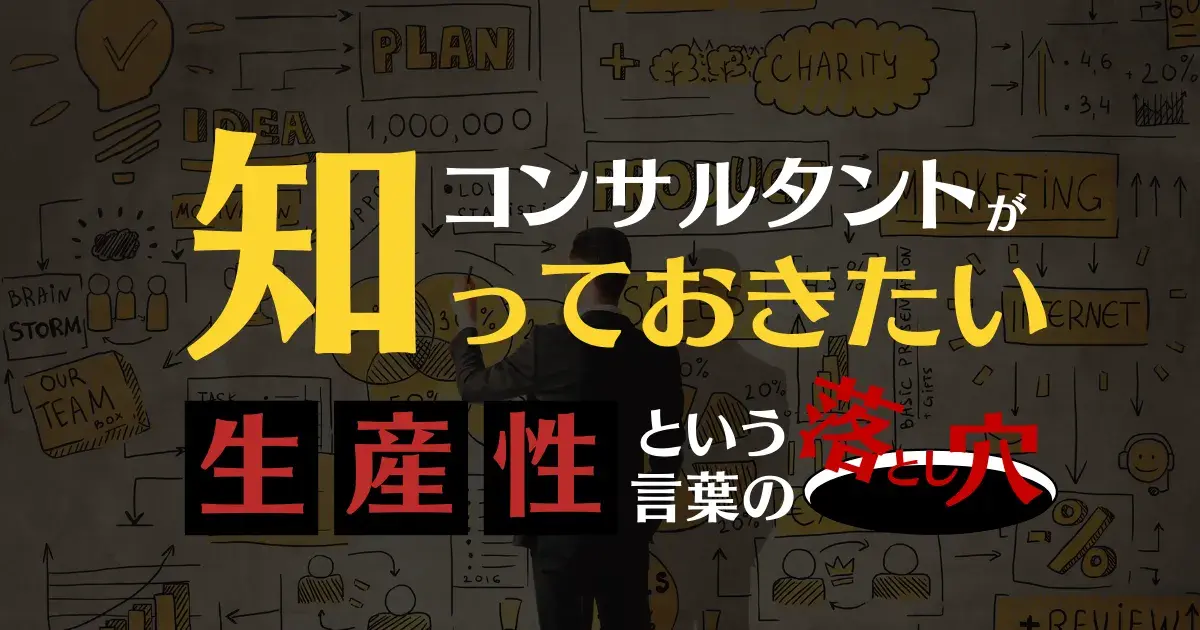
生産性。この言葉、コンサルタント界隈でもよく耳にします。でも、正直に言うと、僕は「生産性」という単語があまり好きじゃないんです。もちろん、無駄な作業を減らすとか、スピード感を持って動くとか、そういう意味では大切な概念だと思います。
だけど、「生産性を上げろ」という言葉をそのまま受け取ってしまうと、かえって自分の価値を下げかねない。
今日はそんな、「生産性」とどう向き合うべきかについて、僕なりの考えをまとめておきます。
生産性とは「答えのあるゲーム」にしか適さない
まず押さえておきたいのは、「生産性」という言葉は、答えが決まっているゲームにだけ通用するということです。
たとえば、表参道から新宿に行くとしましょう。そのとき「どうすれば早く、安く行けるか?」を考える。これはゴールが明確な、いわゆる「答えのあるゲーム」ですよね。こういうときに「生産性」や「効率化」を意識するのはすごく有効です。
でも、僕らコンサルタントが日々向き合っている仕事って、そんな単純じゃない。
「そもそも、どこに行けばいいんだろう?」から考えるのが、コンサルの仕事なんですよね。
だから、「もっと生産性上げろ!」なんて言葉を無邪気に使ってしまうと、答えのない世界を生きる感覚が、どんどん鈍ってしまうんです。
「答えのないゲーム」を楽しむ思考技術
限られた情報からどのようなプロセスでいい示唆や仮説を導き出すか?本書ですべて解説します。「思考って、技術=スキル、後天的に身に着けられるんだ!」って、確信できるはず。この1冊で「考えること」が楽しくなる!
ピカソに「生産性を上げろ」とは言わない
この話をするとき、僕がよく出すたとえがピカソです。ピカソに向かって、「もっと筆のスピードを上げろ」とか「もっと効率よく絵を描け」なんて絶対に言わないですよね。それよりも、「この人にしか生み出せないものを生み出してほしい」と願うはずです。
コンサルタントも同じです。
僕らはアーティストほど劇的じゃないかもしれないけど、「新しい視点」や「新しい切り口」を生み出す仕事をしています。そこに、「生産性」という型にはめる考え方を持ち込むと、むしろ思考の幅が狭くなってしまう。
だから、心構えとしては「答えのないゲームをやっている」意識を常に持つことがすごく大事なんです。
生産性の「分母を下げること」だけじゃ意味がない
もうひとつ、「生産性」という言葉が危ない理由があります。多くの人は、「生産性を上げる=作業時間を減らすこと」と思いがちです。つまり、同じ成果をより短い時間で出せたらOK、みたいな発想ですね。
でも、それだけじゃ全然足りない。
なぜなら、短縮した時間を使って、さらに新しい価値を生み出さなければ、本当の意味で生産性が上がったとは言えないからです。
単に「早く終わった」だけなら、それは「ただサボっているだけ」と何も変わらない。
むしろ、空いた時間で次の価値を生み出す。その意識まで持って初めて、プロフェッショナルだと僕は思っています。
「分母」ではなく「分子」を意識する
もっとクリアに説明するために、こんなふうに考えています。
生産性とは、付加価値(分子) ÷ 時間や労力(分母)
この式で表せます。
- 分母(時間や労力)を減らすだけじゃダメ
- 分子(生み出す価値)を高めることこそ、本当にやるべきこと
つまり、僕らコンサルタントが意識すべきなのは、「どう時間を短縮するか」ではなく、「どう新しい価値を出すか」なんです。
答えのない世界に挑む以上、量やスピードよりも「何を生み出すか」。そこにエネルギーを使っていきたい。
まとめ:答えのないゲームをしている自覚を持とう
コンサルタントという仕事は、効率化のゲームではありません。
誰も正解を知らない中で、仮説を立て、検証し、価値を創り出していく仕事です。
だからこそ、
- 「早くやればいい」ではなく、「新しい付加価値を生み出す」
- 「答えのある作業」ではなく、「答えのない探索」
このマインドセットを忘れないでほしいと思います。「生産性」という言葉は便利だけど、その裏にある落とし穴にも、ちゃんと気づいていたい。これが、僕自身がずっと大事にしている考え方です。