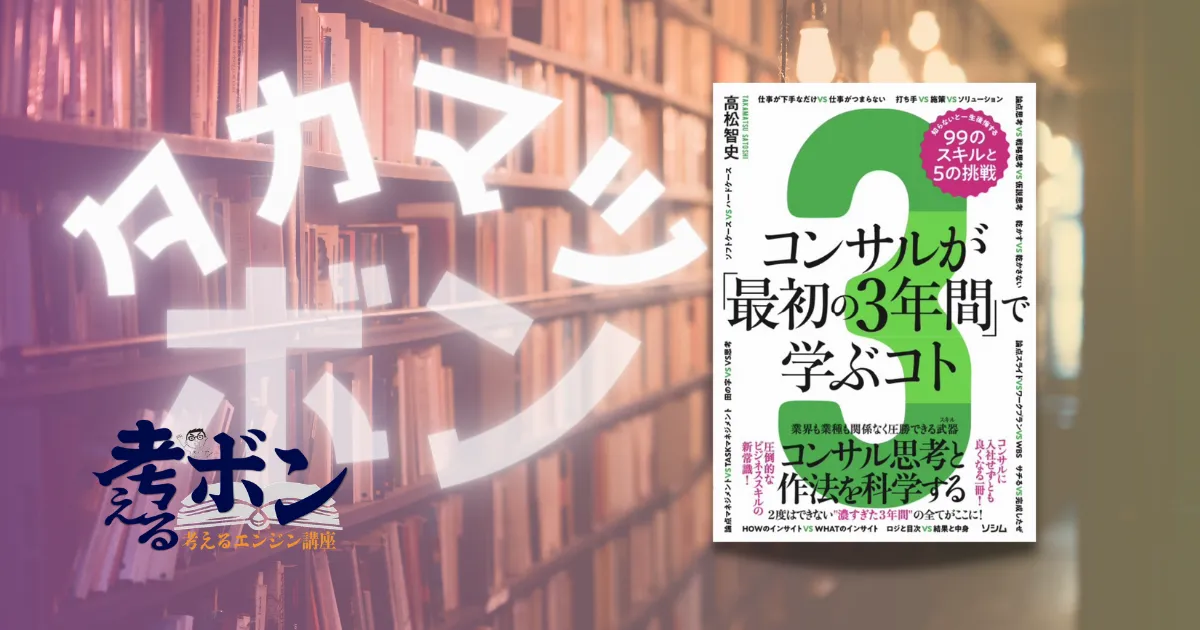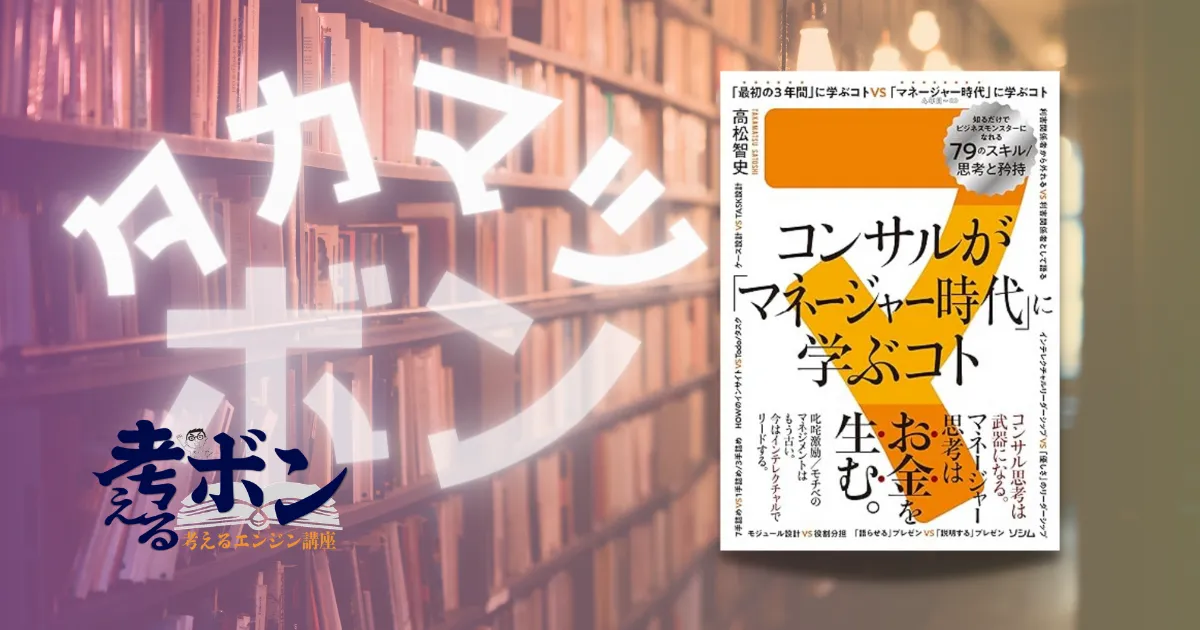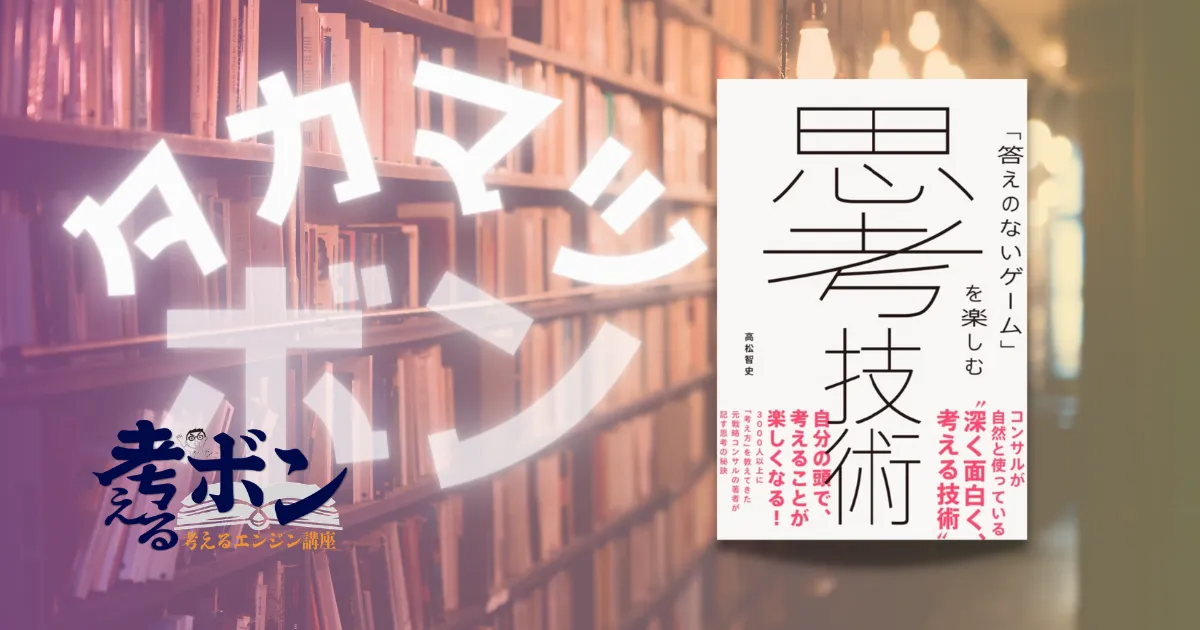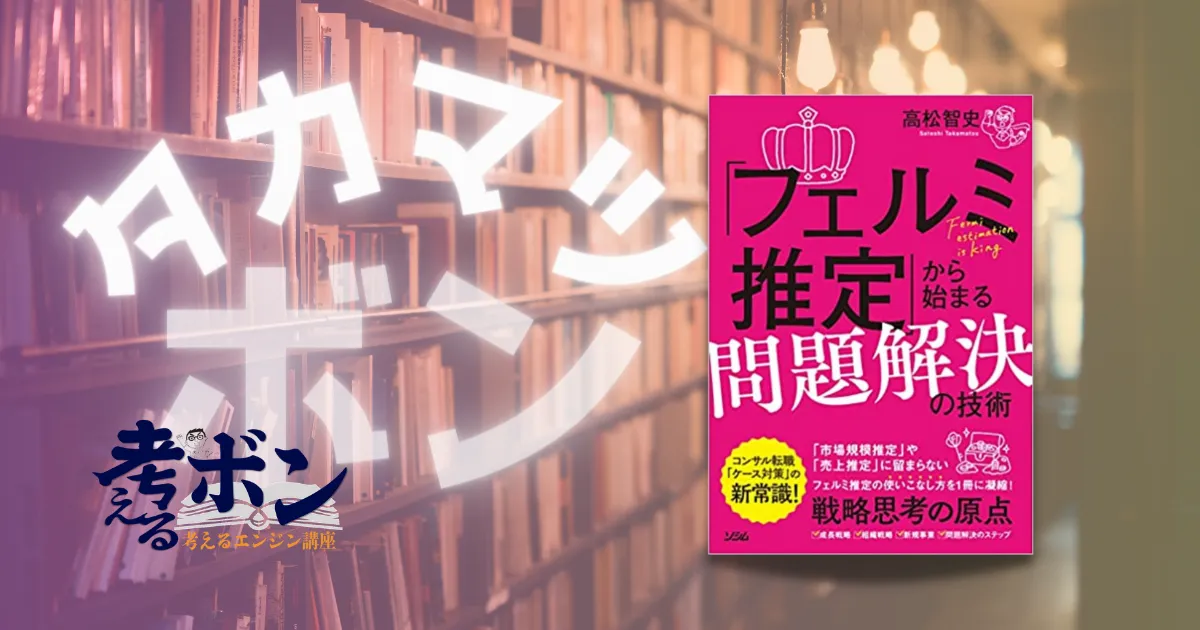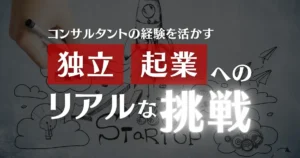コンサルタントの経験を活かす独立/起業へのリアルな挑戦を紹介
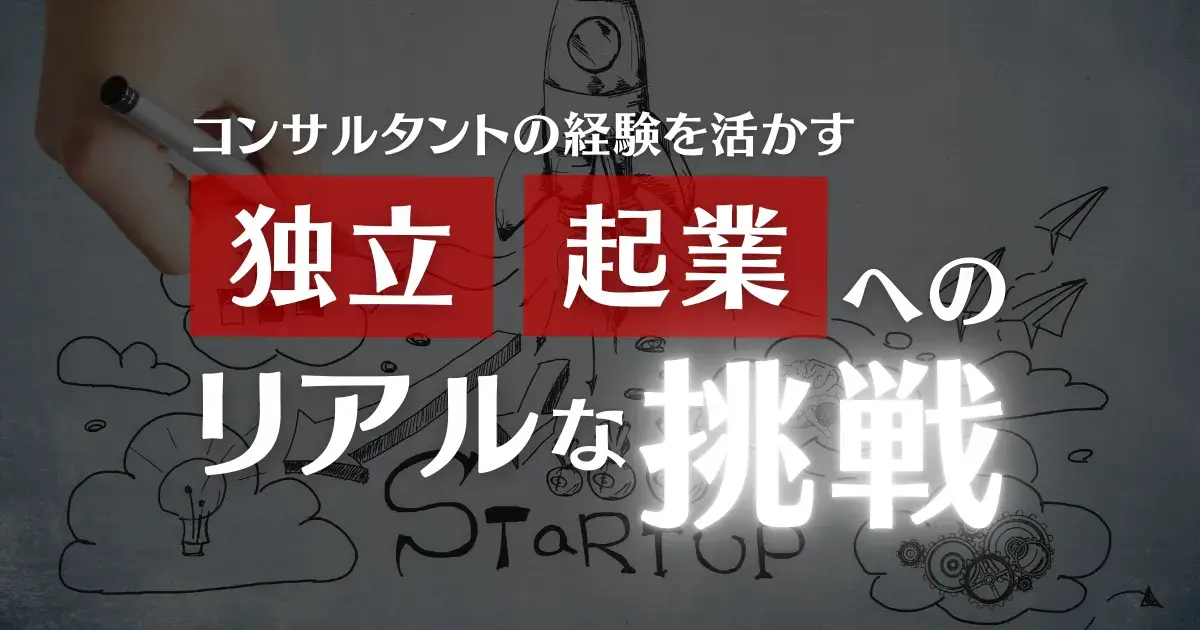
コンサルティングファームでキャリアを積んだ人にとって「いつかは独立してみたい」「自分の事業を起こしてみたい」という想いは少なくありません。とはいえ、安定と組織の後ろ盾を捨てて起業へ踏み出すのは、想像以上に怖さもリスクも伴うものです。この記事は、株式会社Robofull の山本大(おおき)さんとMiletos株式会社の髙橋康文さんという二人のコンサル出身者が独立起業への道をどう歩み、どのような壁や学びに直面したのかを語ってくれた対談動画をテキストにして再編集したものです。
実際にコンサルから事業家へシフトしたときに必要だった心構え、仲間の見つけ方、そしてスタートアップの世界で活かせるコンサルスキルの本質をぜひ感じ取ってみてください。あなたが「起業したいけれど、本当に大丈夫なのだろうか」と不安に思っているなら、きっと背中を押してくれるはずです。
そもそもコンサルから独立/起業はどうなのか?
コンサルタントから独立や起業を目指す人は少なくありません。クライアント企業の課題解決を通じて多彩な業界知識を身につけられたり、プロジェクトが完了すれば高めの報酬を得られることもあり、「十分に貯金したうえで、自分の事業を持ちたい」という考え方も自然に浮かびやすいところです。
ただし、対談の中で高橋さんは「やりたいことがないまま、なんとなくコンサルに入社してそのまま起業しようとする人」は、実際にはあまり成功例を見ていないと語ります。
コンサルティングの現場では、市場規模の大きいビジネスを分析する機会は多くとも、自分が本当に解決したい負との出会いは意外と限定的です。戦略提案や要件定義を繰り返すうちに、さまざまな課題やアイデアを見出せる状況にありながら、実際に「これなら事業化したい」と思えるほどの関心を寄せられるケースが案外少ないのです。
一方で、コンサルの本質的なスキルである分析力や仮説検証のノウハウ、さらに一定以上の収入がある点は、独立や起業を後押ししてくれる強みにもなります。経営理論やビジネスフレームワークに精通することで、おおまかな事業計画を素早く組み立てられるのは大きな利点です。
ただし「起業に必須なのは、市場に存在する負を心から解決したいという意志ではないか」と高橋さんは言います。コンサルファームで築いた知識や枠組みに頼りすぎると、事業を軌道に乗せるうえで本来不可欠な感情面の熱量や現場でこそ得られる視点を見落としかねないのです。
そのため、企業の現場や自分自身の興味領域を掘り下げ、心の底から「これを事業化したい」と思うアイデアを掴んでから起業を選択した方が、長期的には成功しやすいという見方をしていました。
コンサルが「最初の3年間」で学ぶコト
「戦略思考」 =「解、答え、意見、メッセージ」を作り出す考える技術を、「暗記する」=「考える際に自分に問う、声に出して唱える」フレーズを覚えるだけで身につけられる 「思考技術」の本です。
コンサルから独立/起業するために意識すべきこと
起業への準備段階では、「やりたいことがある人を探す」という姿勢がキーポイントとして語られています。コンサルタント同士のネットワークの中には、すでに「この領域で事業を立ち上げたい」という強い思いを持っている人がいるかもしれませんし、クライアントやスタートアップ出身の経営者などとも出会いやすいため、何かしら熱意を抱いている人を見つけることで道が開けるのです。
たとえば高橋さん自身は、偶然にもアクセンチュアのマネージャー向け研修で外部の起業家とつながり、その交流がきっかけで現在の会社を手伝うことになりました。このように、自分の興味や関心を公にしておくと、思いがけない形でやりたいことがある人と巡り合う機会が生まれます。
また、コンサルから独立を考えるなら、プロジェクトを通じて本当に困っている現場をしっかり観察することが大切だという指摘もあります。市場規模の大きさや収益性の高さに目を奪われるより先に、「現場で繰り返されている非効率や不便はないか」「自分が解決したいと強く思える要素は何か」といった視点を持つことで、起業後にブレにくい事業テーマを見つけやすいのです。
さらに、起業には専門的なエンジニアリングスキルが欠かせないケースもありますが、コンサルタントが安易に自分でPythonを学ぶより、エンジニアとの出会いや連携に力を注ぐ方が成果を出しやすい、という実感も語られています。実際、高橋さんの会社でも天才的なエンジニアを巻き込みながら開発を加速し、外から見えない技術領域をカバーしているのだそうです。
コンサルで身につける「分析スキル」や「論点整理力」は、起業にとって非常に有力な武器になりますが、それだけで勝負は難しいのが現実です。信頼できる開発者や経営者仲間とのネットワークづくりを意識しながら、自分のアンテナに引っかかった問題を徹底的に深堀りする。そして、コンサルタントが少し苦手としがちな熱意や感情の部分を大事にすることで、起業後にブレの少ない事業が育ちやすいというのが高橋さんの見解です。コンサルの特性を活かして独立を成功させたいなら、「学んできたフレームワークや分析手法を何のために使うのか」を強く意識することが不可欠だといえます。
コンサルから独立/起業の怖さ
コンサルタントとして現場を経験し、様々なクライアントの課題解決に携わってきた人が、いざ「自分で事業を起こす」となると、途端に押し寄せるのが怖さや不安です。対談のなかで山本さんが正直に語っていたのは、「起業初期は本当に怖かった」という一言でした。
新しいビジネスアイデアを胸に秘めてはいても、それが本当に世の中から必要とされるのか確信が持てないうちは、「周りからバカだと思われるんじゃないか」「自分の考えは単なる妄想ではないか」と疑心暗鬼になるのは自然なことです。
コンサルファーム時代であれば、自分が組織の一員としてプロジェクトに参加し、上司やクライアントと議論を重ねながら正解に近づいていくプロセスが当たり前でした。多少の意思決定ミスや追加工数は組織が補ってくれるため、個人の責任が起業ほど重くのしかからなかったのです。
ところが、独立や起業となると、目指すゴールはまさに自分の頭のなかだけに存在し、周囲に「大丈夫」と言い切ってくれる上司や先輩もいません。コンサル時代には見られなかった孤独感やプレッシャーを一気に背負うため、心の底から「本当にこのままで大丈夫だろうか」という怖さを感じる瞬間が必ず訪れます。
一方で、コンサルファーム出身者が独立の怖さを切り抜けられるかどうかは、意外にも「どれだけ自分の課題意識に確信が持てるか」にかかっている、と山本さんは示唆していました。
コンサルタントとして培った業界知識や分析手法は、起業した瞬間には保証にはなりません。自分が提案するソリューションが実際に収益を生み出し、関わる全員をハッピーにできるかどうかを事前に確証できるわけではないからです。だからこそ、「自分はこの課題を解決したいんだ」とか、「このサービスを心からおもしろいと思うんだ」という意志がなければ、怖さに飲み込まれ、途中で諦めてしまう可能性が高まるのです。
捨てる勇気と全力コミットが生み出す強さ
山本さんは、独立/起業の怖さを乗り越えるために捨てる勇気が不可欠だといいます。
コンサル時代の延長線で「論点を90点にまで磨き上げよう」とこだわる思考法は、スタートアップ環境ではむしろ足かせになりがちです。サービスのアイデアやプロダクトのプロトタイプは、70点でもまず世に出してみる。その後に得られた反応やフィードバックをもとに、必要な部分を改善するほうが、起業においてはスピードも適応力も得られます。
ところが、コンサル出身者はどうしても「論点や課題を丹念に詰めたい」という習性が抜けにくいものです。せっかく作った資料を――ほんの2か月前まではベストだと思っていたアイデアを――いざ捨てるとなると、「こんなに労力かけたのに……」と惜しくなってしまうのです。そこをスパッと捨て、場合によっては別の発想に切り替えられるフットワークの軽さこそが、スタートアップでは重要になります。「怖いからこそ、90点を求めずに小さな成功や失敗を積み重ね、顧客や市場からの実感で補っていく」姿勢を持つことが、コンサルとは大きく異なる起業のリアルなのだと山本さんは強調していました。
“責任”の重みとどう向き合うか
コンサル時代であれば、自分の提案が多少誤っていても、プロジェクト全体の責任をチームが負ってくれたり、パートナーが軌道修正してくれたりします。ところが、起業後はそうはいきません。「自分のアイデアがコケたら、社員を路頭に迷わせるのではないか」「投資家を失望させるのではないか」という恐怖感がダイレクトに襲ってきます。
こうした責任の重さは、人によってはコンサルファームでの仕事のしやすさを恋しく感じさせます。「あのころはよかったな……」と組織に戻りたくなる思いを持つこともあるでしょう。けれども山本さんいわく、その怖さや責任を感じるからこそ、事業家はあらゆるステークホルダーと粘り強く対話し、完全に納得しきれない段階でもとにかく前に進む。コンサルを超える当事者意識とスピード感が身につくのが大きな魅力でもあるのです。言い換えると、コンサル時代の「理論値を詰めてから提案する」のではなく、「提案して走りながら修正し、ステークホルダーと二人三脚でやり遂げる」スタイルにシフトしなければ、事業は軌道に乗らないというわけです。
やりたいことが定まらない恐怖への向き合い方
対談では、「起業したいけれど、本当にやりたいことがないままコンサルに入った人」を少なからず見かけるという話も印象的でした。実際、コンサルという職業は保険のように見えがちで、キャリア市場でも一定の評価が得られます。しかし起業となると、「見込み顧客を誰に設定し、何の負の解消をしたいのか」が曖昧なまま始めるのはリスクが高すぎるため、怖さが増幅します。
山本さんは、そういうときこそ「やりたいことが明確な人と積極的に会いに行き、共感を覚える領域を探す」ことを勧めています。コンサルファームにいるあいだにネットワークを広げ、ベンチャー経営者やスタートアップで活躍している友人・知人に声をかけると、思わぬチャンスに巡り合うかもしれないからです。実際、山本さん自身も偶然の出会いから起業の道がひらけ、「これだ」とピンと来るテーマを共有する仲間に恵まれました。やりたいことがないまま、ひとりで起業を考えるよりも、「すでに熱意を持っている人」と出会い、その情熱に巻き込まれるかたちで自分の道を定めるのが、恐怖を和らげる近道なのかもしれません。
コンサルから独立/起業の怖さは、言うまでもなく大きなものです。けれども「怖いからやめよう」ではなく、怖いと感じられるほどの未知領域に踏み込むからこそ、コンサル時代には得られなかった当事者意識や行動力が手に入るとも言えます。山本さんの言葉を借りれば、「正解を詰めるのではなく、失敗しながら動く。その結果をもとに市場やユーザーと一緒にサービスを育てる」のが起業の醍醐味です。コンサル出身者は往々にして緻密な計画を好みがちですが、起業の初期段階は「70点でもまずリリースする」決断力と割り切りが不可欠。その裏にある怖さをどう扱うか――そこに、コンサルファーム時代とは次元の違う成長機会が待っています。
コンサルタントの独立/起業に失敗しがちな3つの理由
コンサルからの独立・起業を考えていても、実際には十分な成果を出せずに苦しむケースが少なくありません。これまでの対談で山本さんや高橋さんが語った経験から見えてくるのは、単にスキルやネットワークがあるだけでは事業家として成功する保証にならないという厳しい現実です。ここでは、その中でもとくに失敗リスクを高めてしまう3つの要因を整理してみます。
1.「やりたいこと」が曖昧なまま飛び出してしまう
前述(そもそもコンサルから独立/起業はどうなのか?のところで説明しましたが)でも触れたように、コンサル時代に「自分は何をやりたいのか」を見いだせないまま独立してしまうのは、大きなリスクを伴います。コンサルの業務を通じて培った論点整理や問題解決力は、いざ自社事業を組み立てる際にどの領域でどんな価値を提供するのかを決められないと空回りしてしまうのです。「起業したい」という想いだけ先行して、具体的な課題や解決策が定まっていない状態は、事業を軌道に乗せるうえで致命傷になりかねません。
2. コンサル流の「正しさ」を求めすぎる
山本さんが指摘していたように、コンサルタントはどうしても論点を90点にまで磨き上げたくなるという職業病が抜けにくいものです。スタートアップや独立後の事業づくりでは、70点でも素早く試してユーザーからフィードバックを得るほうがはるかに価値があるのに、「もう少し精緻に詰めてから動こう」としてしまい、意思決定と実行が遅れてしまうケースが多く見られます。結果として、市場環境や顧客ニーズへの対応が後手に回り、機会を失うことが失敗につながるのです。
3. 組織の後ろ盾を失った途端、“責任”に耐えられない
高橋さんも「辞めるときに意識していたこと」のなかで少し触れていますが(コンサルを辞める時に意識していたことのところで説明しましたが)、コンサルファームでは自分がミスしても、最終的な責任をマネージャーやパートナー(MD)が負ってくれます。独立すると一転して、すべての結果が自分の責任になるため、想定外のリスクや不測の事態に正面から向き合わなければなりません。強烈なプレッシャーを味わうなかで「こんなはずじゃなかった」と挫折してしまう人がいるのは、決して珍しくないのです。
コンサルから独立/起業のタイミングと注意点
コンサルタントが独立する時期やきっかけは人それぞれですが、「いつ辞めるか」と同じくらい「何を準備して辞めるか」が重要だといえます。山本さんがスタートアップに合流し、さらにロボフルを起業した流れを見ても、タイミングは必ずしも計画通りではなく、偶然の出会いや社内外のネットワークによって左右されている部分が大きいのがわかります。
1. 昇進のステップと独立の関係
コンサルファームでアナリストからコンサルタント、マネージャー、シニアマネージャーと昇進していく道のりは、ある程度明確ですが、そのなかで昇進を待たずに「やりたいプロジェクトが見えたから辞める」「ある程度マネージャーで貯金やネットワークを貯めたから独立する」といった動きをする人もいるのが現実です。山本さんも言うように、マネージャークラス以上になるとある程度お金を貯められるため、自己資金を投入して起業しやすいメリットがありますが、逆にやりたいことがない段階でずるずると役職だけ上がってしまうと、辞めるタイミングを見失う恐れがあります。
2. 「やりたいこと × 強力なパートナー」の組み合わせを先に確保できるか
独立のタイミングを考えるとき、「心から解決したい課題があるか」「共感してくれる仲間やエンジニアなど、コーファウンダー的な存在を確保できるか」が大きな分かれ目になります。山本さんもスタートアップでの出会いがなければ、ロボフルを作るに至らなかったと語っていました。一人でやりたい場合でも、実際には「結局、天才エンジニアが欠かせない」「自分の代わりに資金調達するビジネスパートナーがほしい」といった要件が生じがちです。どちらにせよ、タイミングとしては「仲間やアライアンス先を見つけ、最低限の資金的めどが立ったとき」が独立の踏ん切りをつけやすいと言えます。
3. 準備はしても「完全な安心感」は得られない
どれだけ綿密な準備をしても、独立には怖さがつきまといます(コンサルから独立/起業の怖さのところで説明しましたが)。コンサル時代に築いたネットワークや貯金も、起業後に必ずしも安定をもたらすとは限りません。ただし、もし起業で失敗したとしても、コンサル出身者なら「再就職や別の事業への転身はむしろスムーズにできる」という見方もあります。100%の安心を求めすぎると、いつまでもファームを辞められないので、70~80%の納得感で一歩を踏み出すのが現実的だといえます。
まとめ: コンサルタントとして起業に成功するためのポイントとは?
ここまで山本さん、高橋さんとの対談を踏まえ、コンサルから独立・起業をするうえでの怖さや失敗リスク、そしてタイミングや注意点を見てきました。改めて整理すると、コンサルタントとして起業を成功させるためのポイントは以下のようになります(既に触れた内容との重複がありますが、最終まとめとして改めて挙げます)。
まず第一に、「本当に解決したい課題があるか」をしっかり自問する必要があります。コンサルで身につけたロジカルシンキングや分析力は貴重な武器ではあるものの、やりたいことが定まっていない状態で起業に踏み切ると「何をサービスにするか」が曖昧なまま時間が過ぎ、心身ともに疲弊しがちです。
第二に、完璧を求めすぎずに小さな実行を重ねる姿勢が欠かせません。コンサルタントは90点のプランをまとめがちですが、スタートアップ・独立後はフィードバックを素早く得るためにも70点でプロトタイプを出し、市場の声を聞きながら再設計するほうが効果的です。これに慣れないうちは怖さが伴いますが、そこを割り切れるかどうかが事業家への変身の大きなカギになります。
第三に、「一緒に戦ってくれる仲間をどう見つけるか」が重要です。エンジニアやデザイナー、あるいは資金調達や営業に長けたパートナーを確保できないまま単身で立ち上がると、サービス開発やユーザとの接点が思うように拡張できず、早い段階で詰まってしまうリスクが高まります。コンサル時代の人脈を活かして、やりたいことを明確に発信し、共感してくれる人と出会う努力が必要です。
そして、多少の準備や貯金をしても、怖さは完全になくならないということを受け入れるのが大前提です。コンサルファーム内で積み上げた実績や肩書きがあっても、実際にサービスを売る段階では数字がすべてと言っても過言ではありません。そうした厳しい環境に飛び込むことで、コンサル時代には味わえなかった当事者意識や加速度的な成長を得られるのも事実です。完璧主義を少し捨て、意思決定と行動スピードを上げる覚悟こそが、起業を成功へと導く最大のポイントといえます。
コンサルが「最初の3年間」で学ぶコト
「戦略思考」 =「解、答え、意見、メッセージ」を作り出す考える技術を、「暗記する」=「考える際に自分に問う、声に出して唱える」フレーズを覚えるだけで身につけられる 「思考技術」の本です。
コンサルが「マネージャー時代」に学ぶコト
10万部を超えた『コンサルが「最初の3年間」で学ぶコト』の続編であり完結編にして、過去最高傑作。400ページにもわたる至高の “熱き講義形式” ボン。
コンサルタントが『マネージャー時代』に学ぶコト、学ぶべきことを詰め込んでおります。
「答えのないゲーム」を楽しむ思考技術
限られた情報からどのようなプロセスでいい示唆や仮説を導き出すか?本書ですべて解説します。「思考って、技術=スキル、後天的に身に着けられるんだ!」って、確信できるはず。この1冊で「考えること」が楽しくなる!
「フェルミ推定」から始まる問題解決の技術
「フェルミ推定」は、市場規模推定や売上推定を算出する為だけの思考法じゃありません。成長戦略、新規事業などに幅広く応用できる、いわば戦略思考の原点とも言えます。そして、その考え方を丸っと凝縮して一冊にまとめたのが本書です。