コンサルから事業会社へ転職するには?志望動機やスキルの活かし方と注意点

コンサルタントとして培った論理思考やプロジェクト推進力は、実は事業会社でも大いに活きる資産です。短期間で成果を出すことに慣れたコンサル出身者が、長期視点で事業を育成する現場に移ることでどんな相乗効果が生まれるのか、また逆にどのようなギャップに苦戦するのか――本記事では、「コンサルから事業会社へ」というキャリアチェンジを検討するうえで押さえておきたいポイントを幅広く取り上げます。
志望動機、事業会社へ行くデメリットや具体的な活かせるスキル、転職後にさらにステップアップする方法までを解説していますので、ぜひ転職活動やキャリア形成の参考にしてみてください。
コンサルと事業会社の共通点
コンサルティングファームと事業会社は、アプローチは異なるものの、最終的にはいずれも社会や顧客に価値を創出し、課題を解決することを目指しています。コンサルファームはクライアント企業を通じて社会に影響を与え、事業会社は自社のプロダクトやサービスを直接、顧客に届けて価値を提供します。
また、どちらの組織でも専門性を活かしたチームワークが求められ、個々のスキルを掛け合わせることで成果を出すことが不可欠です。そして、両者ともに、改善や成長への意欲が組織を動かし、市場の変化に対応し続ける姿勢を持ち合わせています。
コンサルティングファームも事業会社も、最終的には「社会や顧客に価値を提供する」ことをゴールとしており、そのために専門性を掛け合わせながらチームで成果を生み出す姿勢は共通しています。さらに、「現状をより良くできるはずだ」という向上心をエンジンに、常に新しい手法やテクノロジーを取り入れながら組織全体の改善・成長を続ける点も、両者に共通する大きな特徴と言えます。
コンサルと事業会社の違い
コンサルティングファームと事業会社の違いは、主にプロジェクトの時間軸や成果の追求の仕方に際立った違いがあります。コンサルファームでは、短期プロジェクトに集中し、3〜6か月の期間で成果を上げることが求められます。プロジェクトごとに新たなメンバーが組まれることが一般的で、迅速な結果を求められます。
一方で、事業会社では、同じメンバーが長期的に事業に関わり、そのビジョンのもとで一貫して成果を積み上げていく文化があります。より長期的な視点で事業を育て、持続的な成長を目指すため、メンバー間での円滑な協力や組織の中での調整が重要になります。
また、コンサルティングファームは3~6か月の短期プロジェクトで集中して成果を出し、プロジェクトが終わるとチームメンバーが再編成されるケースが多いのに対し、事業会社では同じメンバーが長期的に同じビジョンを共有しながら事業を育成するため、長期的な成果を重視しやすいという大きな違いがあります。

コンサルから事業会社への転職志望動機
事業会社への転職を考えるコンサルタントにとっては、「もっと経営の当事者意識を持ちたい」「大きな成果を自分の手で形にしたい」など、さまざまな動機があるでしょう。ここでは、コンサルから事業会社に行く代表的なメリットをまとめました。
なお、コンサルで得たスキルや経験がどのように活かせるかは、この後の「コンサルの経験が事業会社で活かせるスキル」で詳しく解説しますので、あわせてご覧ください。
当事者として成果を直接感じられる
コンサルタント時代は、クライアントに提案を行っても、その実行フェーズや成果が目に見える形で返ってくるまでにタイムラグが生じたり、自分の手を離れた後の効果を実感しづらい面があります。事業会社であれば、自ら立案・実行し、その結果が売上やユーザー数、組織改革などとしてダイレクトに現れるため、大きな達成感を得やすいのが魅力です。
長期視点でのキャリア形成が可能
コンサルティングファームでは、プロジェクト単位で評価されることが多く、短期的な成果重視の色が強いです。一方、事業会社では中長期的な事業計画や組織づくりを見据えながら、自分のキャリアをじっくりと育てられます。数年先を見越して新規事業を育成したり、経営幹部候補としてマネジメントスキルを伸ばす道も開けるでしょう。
制約が少なく実行に移しやすい
クライアント企業に対しては、コンサルタントとして中立的な立場を守りながらベストプラクティスを提案しますが、実際にどのベンダーを採用するかなどの最終決定はクライアント次第です。事業会社では、自社プロダクト・サービスに直接関わるため、自分のアイデアをスピーディーに試せるのが大きなメリットです。上司や社内の承認さえ得られれば、実行フェーズにすぐ移れるケースが多くなります。
組織の「顔」として責任と裁量が大きい
コンサルタント時代は客観的アドバイザーの立場でしたが、事業会社では社内外で「自分が当事者」としての責任を負います。これはプレッシャーにもなりますが、その分裁量が大きく、リーダーシップを直接発揮しやすいのが特徴。組織の中核メンバーとして事業を動かす実感を得られるでしょう。
コンサルから事業会社に行くデメリット
コンサル出身者が事業会社へ転職すると、期待通りのスピード感や裁量が得られない場合もあります。以下では、その主なデメリットや注意点を整理しました。
なお、実際に転職する際の心構えや、事業会社特有の文化への適応方法については、この後の「コンサルから事業会社に行く時に意識すべきこと」でも言及しますので、あわせてご確認ください。
迅速な成果が求められるプレッシャー
コンサルタントから来た人は、「即戦力」として大きな期待を寄せられることが多く、短期間で成果を出すよう求められる場合があります。特に30代後半以降で転職した場合は管理職としての役割を期待されるため、自分の強みを短期でアピールできないと「思ったほど活躍していない」と判断されるリスクがあります。
社内調整や既得権益の壁
コンサルが提案書の完成度とロジックに集中できるのに対して、事業会社はすでに動いている組織構造や人間関係、既存ルールとの衝突を避けられません。プロジェクトが進まない原因が「根回し不足」「部署間の利害対立」など、一見ロジカルではない部分にあることもしばしばで、思った以上にストレスを感じるかもしれません。
年収や肩書きが下がる可能性
コンサルタントは年功序列に縛られにくく、高い報酬水準が設定されている場合が多いです。事業会社によっては、コンサル時代より年収や肩書きが下がることもあり、特にスタートアップや新規事業の場合は給与を抑えつつ株式やストックオプションで補填するケースがあるなど、報酬体系が大きく変わる可能性があります。
「何でも自分でやる」必要性に戸惑う
コンサルティングファームではサポートスタッフや専門チームが充実しており、プレゼン資料やリサーチなどを分業しやすい環境です。しかし、事業会社では、企画立案から資料作成、マーケティング、時には雑務的な作業まで幅広く自分で対応する必要が出てきます。
最初は「こんなことまで?」と戸惑うこともありますが、逆に言えば手触り感のある仕事を経験できるチャンスともいえます。
事業会社への転職で役立つ志望動機の考え方
「事業会社に転職したい」と思っていても、実際の面接では「なぜ、弊社なのか?」「あなたが入社してどのように活躍できるのか?」といった問いを、論理的かつ具体的に答える必要があります。
単なる熱意や「他社ではなく御社を選びました」という言葉だけではなく、どれだけ自分自身の“考える力”や業界・企業研究を踏まえてその結論に至ったのかをアピールすることが重要です。以下では、事業会社への転職時に志望動機を作成する際の具体的なポイントと、その背景にある考え方をまとめました。
志望動機が重要な理由を理解する
転職活動の中でも、事業会社が候補者を評価する際は「なぜこの会社を選んだのか」を掘り下げて聞くことが多いです。単に「御社のビジョンに感銘を受けた」などの情熱的なフレーズを並べるだけでは、どれだけ情報収集や考察を行ったのかが伝わりにくい場合があります。
- 論理的なアピールが求められる理由
- 事業会社は、入社後に“当事者”として成果を出せる人材を求めています。
- 「なぜ、この業界・この企業を選ぶのか」をデータや業界知識を踏まえてしっかり説明できることは、企業研究や自己分析を丁寧に行っている証拠でもあります。
- 面接官は、あなたの思考プロセスそのものに興味を持ち、「転職後も同じアプローチで仕事を進められるか」を見極めようとしています。
何を見られているのか―ロジックの組み立て方
事業会社の採用面接では、「なぜわが社に入りたいのか」「具体的にどんな経験を活かすのか」といった質問に対して、思考の過程と情報収集の質を見られています。自分が行った事業調査や、業界に対する理解をどう組み立てて志望動機に反映させているかが問われるのです。
- 情報収集と自分なりの分析
- 企業の公式サイトやIR資料、業界レポート、SNSなどから情報を収集し、何が今後の成長ドライバーになり得るかを読み解く。
- 「どんな課題があると思うか」「自分の経験をどう活かせるか」を具体的に整理しておき、志望動機に紐づける。
- 自分の強みとの接点を明確化
- 「その企業が目指しているビジョンや取り組み」と「自分が培ってきたスキル・経験」の相乗効果を論理的に示す。
- たとえば、データ分析が強みなら、具体的にどうやって今後の事業課題解決に貢献できるのかをエピソード付きで語る。
志望動機のアピールポイント
志望動機では、熱意とともに「どれだけ戦略的に考えて動いているか」を示すことが肝心です。まず「なぜ、事業会社(あるいはこの業界)を選ぶのか」を論理づけ、それを踏まえて「なぜこの企業なのか」を説得力ある形で語る二段構えが効果的です。
- なぜ、事業会社に行きたいのか
- コンサルタントとの比較で「より長期的な視点で事業を育てたい」「自ら当事者として成果を生み出したい」といったモチベーションを明確にする。
- 過去の経験(プロジェクト経験やクライアント先での学び)を踏まえ、「自分はこういう強みがあって、事業会社の現場でこそ活きる」と論じる。
- なぜ、その企業を第一志望にしているのか
- 企業のビジョンや成長戦略、近年の取り組みをリサーチし、具体的に何に共感しているか、どこで自分が活かせるかを示す。
- その企業ならではのユニークな強みやカルチャーを理解したうえで、自分がどんな価値をもたらすかを“データ”や“エピソード”と併せて伝える。
「第一志望」であることを明確に示す
多くの企業は、面接に来た候補者が「本当に自社で活躍したいのか」を気にします。複数のオファーを受ける可能性がある転職市場で、第一志望の候補者ほど入社意欲が高く、早期離職や内定辞退のリスクが低いと判断されやすいのです。
- 第一志望を示す際のポイント
- 「ここで働くことが自分にとってどんな意義を持つのか」を論理的に語る。
- 競合他社と比較しつつ、なぜこの企業が魅力的なのか(製品、技術力、カルチャー、将来性など)を具体的に説明する。
- 自社への特別な熱意を感じさせるキーワードや具体例を入れ込み、面接官に「この人は本気だ」と思わせる。
志望動機作成の黄金ルール
志望動機は「形だけ」の答えではなく、しっかりとした準備と工夫によって作り上げるものです。事業会社への転職を目指すなら、業界・企業研究から自己分析まで、論理的に組み立てるプロセスを大切にしましょう。
- 情報整理と再構築
- 「自分が得意とするスキル・経験」「相手企業のビジョンや戦略」「業界全体の動向」を整理し、その3つの交点に焦点を当てる。
- 最終的に「あなたが活躍することで企業がどんな価値を得られるのか」をストーリー仕立てで伝えると、説得力が増す。
- 具体的な事例や数字を取り入れる
- 過去の実績や具体的なプロジェクトでの成果を、数字やエピソードで語ると、面接官にとってイメージが湧きやすい。
- 企業研究の結果なども「○○の新規事業が△年で××億規模に成長した背景に興味を持ち、自分もその推進に貢献したい」といった形で活用する。
参考資料や業界書籍を活用する
事業会社の多くはプレスリリースやIR情報、社長のインタビュー、採用ブログなどを積極的に発信しています。志望動機を具体化するには、こうした一次情報に加えて、業界の主要書籍やニュースサイトなどをチェックして、独自の分析を行うのがおすすめです。
情報ソースの例
- 企業公式サイト・IRレポート・投資家向け説明会資料
- 業界専門誌や海外のニュースサイト
- SNS(TwitterやLinkedIn)で経営陣や従業員の発信を追う
コンサルから事業会社に転職する時に意識すべきこと
コンサルティングファームから事業会社へ転職するのは、年齢や家族構成、キャリアプランなどによってハードルの高さや考慮すべき点が変わってきます。特に30代以降になると、しがらみや責任が増し、慎重にならざるを得ない場面も増えるでしょう。以下では、実際にコンサルから事業会社に移った方の経験談やポイントを踏まえたうえで、「転職時に意識しておきたいポイント」を整理します。
自分なりのセーフティーネットを用意しておく
収入・生活面の余裕
コンサルを辞めて事業会社へ行く際、最初から高待遇が保障されるわけではありません。給与が下がるケースも十分考えられるため、一定の貯蓄やサイドビジネスなどで生活に余裕をもたせると、転職先で思い切りチャレンジしやすくなります。
「戻る先」を確保しておく
「失敗したら戻ってきてもいいよ」という前職の上司や社内での人脈を持っていると、新天地でもリスクを恐れず行動しやすくなります。コンサルは人材価値が高いため、まったく別のコンサルファームや別業界への転身もしやすいです。
肩書きや役職にこだわりすぎず、でも見極める
どのポジションで入社するかを交渉する
事業会社側での肩書き(CXO、マネージャーなど)は、その後のキャリアにも影響します。コンサルの「マネージャー」で退職すれば、転職市場や社内で「このポジションだった人」として一定の評価が得られることも大きいです。
“肩書き=現場での成果”ではないが武器にはなる
事業会社で実際に成果を出せるかどうかは別問題ですが、スタートアップなどに参画する際は「CXO枠」や管理職ポジションで入社できると、社内外でのコミュニケーション・リーダーシップを発揮しやすいのも事実です。
年齢が上がるほど「即戦力」「リーダーシップ」を求められる
若手ならポテンシャル採用もあり
25~26歳や30歳前後なら、まだ学ぶ余地や潜在能力を評価されて事業会社に入りやすい。逆に30代後半以上になると「入社後すぐに活躍できるか」が厳しく問われます。
家族や住宅などの固定費増加にも注意
30代後半以降は家族を抱えている場合が多く、収入面や生活リズムの大きな変動がリスクになりがち。事前に貯蓄や家族の同意、在宅ワークの可否などを調整しておくと安心です。
まずはお手伝いや「部分的な関わり」から始める
副業・プロボノ的なアプローチ
いきなりフルタイムで事業会社に飛び込むより、コンサル在職中に週末やアドバイザー的な立ち位置で関わりを持ってみる方法があります。小規模でも自分のビジネスを試しに立ち上げる、スタートアップのメンターを引き受けるなどで実践感覚を培うのです。
事業会社側も受け入れやすい
部分的な参画から始めることで、事業会社側もあなたのスキルを見極められ、マッチしそうなら正式にオファーがくるかもしれません。いきなり正社員での“重役ポジション”を狙うより、段階的に信頼を築くやり方も有効です。
長期視点でキャリアを捉え、失敗を恐れすぎない
いつでもやり直せるマインド
コンサル出身者には一定の市場価値があるため、たとえ事業会社で上手くいかなかったとしても、再びコンサルへ戻る道や他の会社でマネージャー職を目指す道もあります。失敗を恐れずに挑戦しやすいのがコンサルの強みとも言えます。
やりたいことを試す→成果を次のステップへ
自分が興味を持ったサービスや領域でどれだけ実績を残せるか。事業会社での成果は、その後の起業や別分野への展開にも活きます。長期的に見れば、一度の失敗や遠回りも大きな経験値になるでしょう。
組織の壁や現場目線を意識して動く
コンサルとは違う権限・制限がある
事業会社では、社内に既に既得権益や部門間の複雑な調整が存在します。コンサル時代のように提案が通って即動けるとは限らないため、上司や他部署、現場スタッフの理解を得ながら進めるコミュニケーションが必要です。
現場との関わり方を柔軟に
コンサル出身者はロジカルな提案力は強みですが、現場が抱える実務の苦労や人間関係への配慮が疎かだと反発を招く恐れも。提案だけでなく、どこまで一緒に手を動かすかという姿勢が信頼構築のカギになります。
コンサルの経験が事業会社で活かせるスキル
仮説検証型の思考・問題解決力
コンサルタントは経営課題に対してまず仮説を立て、情報収集や分析を通じてその仮説を検証し、最適解を導くというプロセスを常に回しています。これは不確定要素が多い事業会社の現場でも有効です。たとえば、完璧な情報が揃わなくても「まずは70点の見解を出して素早く動き、実地の検証から学びつつ柔軟に方向転換する」という姿勢は、急激に市場環境が変化する場面やサービス拡大フェーズなどで大いに役立ちます。また、「どのデータを、どの順番で見れば意思決定しやすいか」を構造的に考えられるため、短時間でチームを説得し、合意形成を進めるうえでも強みとなります。
一歩踏み込んだコミット力・主体性
コンサル時代に培った「クライアントの立場に立ち切る」姿勢は、事業会社においては「自分事として責任を負う力」へと転化されます。コンサル時代は客観的に提案していたかもしれませんが、事業会社ではユーザーや社内の現場と深く関わり、課題に対して情熱や感情移入をしながら積極的に動く姿勢が求められます。たとえば、上司の何気ない一言に気づいて課題を先回りして解決したり、自ら担当外の問題でも必要とあらば飛び込んだりすると、周囲の信頼も得やすく、組織全体を巻き込む推進力を発揮できます。
ロジカルシンキング & ドキュメンテーション
コンサル出身者は論理的に思考し、わかりやすい資料をスピーディーに作成する習慣が身についています。事業会社では特に、経営陣や他部署との意思決定で短時間にポイントを把握してもらう必要があるため、筋道立てた提案書やプレゼンの作成力が重宝されます。たとえば「どこが問題で、どの施策を実行すれば改善するのか」といったストーリーを整理し、短時間で説得力を持って説明できる点は、部門横断プロジェクトのリードなどで大きな強みとなるでしょう。
マネジメントの基礎力(スケジュール・タスク管理)
コンサルティングプロジェクトでは、限られた期間で成果を出すためにスケジュール管理やタスク分解、チーム内外の調整を徹底します。この経験は事業会社へ転職した後も大いに活かされます。期限から逆算して必要な工程を洗い出す、日程やリソースの制約を踏まえて優先順位を付ける、取引先との交渉を厭わず行うなど、「プロジェクトをきちんと前に進められる人物」として評価されるでしょう。
「脳内の仮想上司・クライアント」を活用した仮説思考
コンサル時代、上司やクライアントの視点を自分の中に取り込んで「この人ならどう考えるか」「どんなツッコミを入れそうか」とイメージする習慣は、事業会社でも有用です。新しい施策を検討する際、社内外のキーパーソンや役員、ユーザーの立場から見た場合に何が問題になりそうかを想定することで、抜け漏れを減らし、より多角的な判断を下せます。複数の視点を頭の中で切り替えながら検討することで、スムーズに合意形成やリスク管理を進めやすくなります。
仕事の枠を取り払う“何でもやる”姿勢
コンサル時代に身につく「課題解決のためなら、どんな方法でも構わない」という姿勢は、事業会社でも大きな強みになります。情報が見つからなければ図書館や地元のよろず屋に依頼してでも探すなど、一見泥臭くても成果につながるなら惜しまない柔軟さが、事業会社の現場で新たなチャンスを切り開くきっかけとなるでしょう。部署間の折衝や、顧客企業との交渉など、一見“雑用”に見える作業も進んで行うことで、結果的にネットワークを広げ、事業成長に寄与する大きなノウハウを得られます。
感情を伴った問題発見力・コミットメント
コンサルは理詰めでクールに見られがちですが、実は課題解決には気度哀楽を伴うことが少なくありません。事業会社でも「自分が興味や違和感を感じる部分」こそが改善のヒントになるため、ポジティブ・ネガティブ問わず感情を前向きに活かす姿勢が重要です。たとえば「この仕様はユーザーが使いにくいのでは」といった直感や不満を放置せず、具体的な対策や提案につなげることで、周囲の共感を得やすくなり、組織を巻き込んだ改善が進められます。
事業会社でさらにステップアップするために
「枠にとらわれず行動する」×「感情を使いこなす」
事業会社では短期的に売上や利益などの数字を求められる一方で、組織の成長や人材育成など長期的な視点も欠かせません。その両方をバランスよくこなすために、コンサル時代に培った「どんな方法でも成果につなげる柔軟な姿勢」と、自分や周囲の感情を理解・活用する力が大きな武器になります。
たとえば、プロジェクトが思うように進まない場合、単に資料不足やスケジュールの問題と片付けるのではなく、「本音では誰が何を気にしているのか?」といった感情面にも目を向けることで、真のボトルネックを見つけやすくなります。さらに、部署間の調整や市場調査など、本来は担当外とされる業務にも積極的に踏み込み、社内外の状況を深く知ることで、新しいチャンスを生み出すことが可能です。ポジティブ・ネガティブ問わず生まれる感情を前向きに転化して課題発見やモチベーションに変えることで、周囲を巻き込みやすくなる点も大きな強みと言えるでしょう。
ビジネスサイドの視点+“エンジニア的”視点で新価値を創造
コンサルタントには戦略的・論理的なアプローチが求められる一方、エンジニア出身者であれば実装面のリアリティを同時に考慮できます。この両方を掛け合わせると、事業会社では「経営レベルの視点」と「技術レベルの現実性」をつなぎ、より説得力のある施策やプロダクトを生み出せます。
たとえば新サービスのビジネスモデルを検討するときに、要件定義や開発工程まで踏み込んで考えることで、スムーズなロードマップを提示できるうえ、ユーザー体験や使いやすさの観点も議論に盛り込めます。単にデータ分析や戦略論だけでなく、ユーザー視点や実装の難易度なども加味した提案は、社内外の理解を得やすく、実行段階でのブレを最小限に抑えられるでしょう。
プロセス重視から「結果重視」へのマインドセット変換
コンサル時代は「論理的に正しい提案」や「プロセスの整合性」が高く評価される反面、事業会社では明確な数字や成果が求められます。ロジックだけでは動かない相手やシチュエーションが往々にして存在するため、必要であれば泥臭い行動も辞さず、「結果を出すために最善を尽くす」姿勢が大切です。
具体的には、情報不足なら図書館や地域企業へ直接足を運ぶなど、一見遠回りと思える手段も躊躇せずに活用すること。計画どおりにいかない場合も、一旦プライドを捨てて周囲のサポートを仰いだり、素早く方針転換を図ったりする決断力が不可欠です。さらに、半年~1年スパンで目に見える成果を積み重ね、「やると決めたら実行する人」という評価を得ることが、組織内の信頼を高め、次のステップを切り拓くカギになります。
学んだことを“頭の中にストック”し続ける
コンサルファーム出身者がよく実践しているのが、日々の学びを意識的に積み上げる習慣です。上司やクライアントから受けたフィードバック、成功事例や失敗事例、フレームワークなどをメモやツールで残し、必要なときに素早く引き出せる“脳内の引き出し”を増やします。
たとえば、プロジェクト終了後に上司やクライアントの口癖や論点・成功失敗の要因を簡潔にまとめておく、週に一度「3つの学び」を振り返るなど、やり方は人それぞれ。転職後も過去のメンターや上司の思考法を思い出すことで、混乱しがちな新環境でも落ち着いて課題に向き合えるというメリットがあります。
70点で動き、検証しながら走る実行力
コンサルタントは90点~100点の完成度を目指しがちですが、事業会社ではスピードを重視し、70点でもまず動き、走りながら軌道修正する手法が効果的です。データ分析やユーザーのフィードバックを即座に取り入れ、必要なら方向転換する柔軟さが、ビジネス機会を逃さないためのポイントとなります。
時には「その課題、実は本当に重要か?」を都度見直すことで、リソースを最適配分しながら成果を上げられるでしょう。
チームを巻き込み、異なる視点を取り入れる
コンサルティングファームでは個人の思考力が重視される場面も多い一方、事業会社では周囲との連携や合意形成が極めて重要です。自分と立場や専門分野の異なるメンバーこそが新たな発想やアイデアをもたらしてくれるため、積極的に意見を聞き、あらかじめ叩き台となる提案を用意したうえで相手の考えを取り入れる姿勢が欠かせません。苦手意識を持つ相手とのディスカッションからこそ、大きな学びや革新的な着想が得られる場合があります。
捨てる勇気を持ち、柔軟に方向転換する
コンサル時代に練り上げた計画やプランも、実際に動かしてみると想定外のリスクや新機会が次々に現れるのが事業会社の現場です。そこで必要なのが、過去のこだわりやプライドを捨て、事業利益や組織成長を最優先に再設計する勇気。
たとえば「自分が2か月かけて考えた施策だから」という理由で固執せず、成果が期待できないと判断したら潔く手放す、逆に新メンバーを迎えるなど大きく方針を変えるなど、状況に応じて速やかに組み替えられる人ほど、事業会社で大きな成果を出しやすいと言えます。
目に見える成果を意識し続ける
事業会社では、コンサル時代のように「提案の完成度」だけで評価されるわけではなく、売上や利益、ユーザー数などの定量的成果が常に求められます。そのため、自分が担当するタスクや施策がどのKPIに結びつくのかを常に意識して動くことが重要です。
実績を社内外にきちんと共有し、「〇〇のプロジェクトで売上を○%伸ばした」「新規サービスのユーザー数を△万人まで拡大した」といった具体的な成功事例を可視化できると、次の予算やリーダー職への抜擢など、キャリアアップのチャンスも広がるでしょう。
考えるエンジン講座の紹介
論点思考を身に付けることで“考え方”と“伝え方”を進化させ、コンサルタントを超えるビジネスパーソンを目指すプログラムです。すべての講義は代表のタカマツが1対1で対応し、ロジカルシンキングやクリティカルシンキングとは異なる「論点思考」という核となるスキルをマンツーマンで伝授します。
単に知識を増やすだけではなく、“考え方を変え、行動を変える”ことをゴールとしています。コンサルタントを凌駕するビジネスパーソンとしての飛躍を目指すなら、ぜひ一度無料相談でご自身の課題を整理してみてください。明日からの仕事に直結する、新たな視点やスキルが得られるはずです。
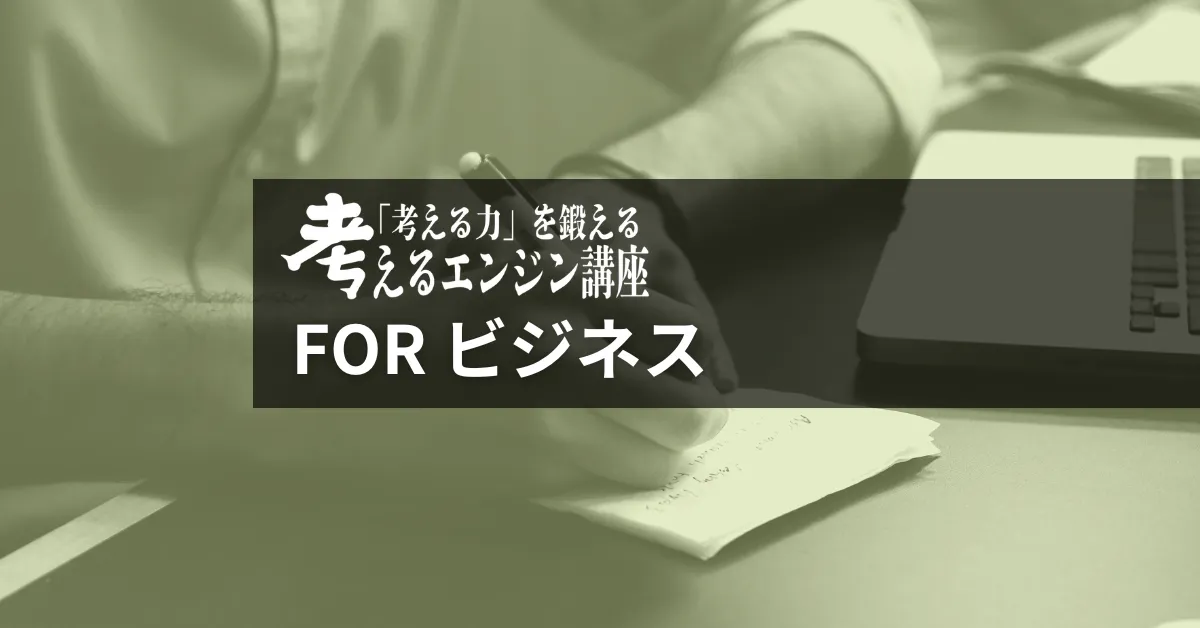
「タスクベース」から「論点ベース」の考え方、働き方へ。「論点思考」(≠ロジカルシンキング)を身に着け、指示待ち人間/作業屋から脱し、自ら考え、上司/顧客と「論点ベース」の議論(≠タスクベースの議論)を習得できる、世の中で唯一無二の講座です。
最後に
コンサルから事業会社への転職は、短期志向から長期志向への切り替えや、実際に自社で成果を追うプレッシャーなど、新たな学びと挑戦が待っています。一方で、コンサルならではの仮説検証型の思考力やロジカルなプレゼンテーションスキル、泥臭い情報収集を厭わない柔軟性などは、事業会社でも強みとして大いに評価されるでしょう。
自分の得意分野や志向を活かしてどのように貢献できるのかを明確に描き、入社後は「当事者意識」を持って行動することで、一見かけ離れているように見える2つの世界をスムーズにつなげられます。コンサル経験を新たなステージで花開かせたい方は、本記事で紹介したポイントを踏まえながら、ぜひ行動に移してみてください。きっと、事業会社でも大きなインパクトを生み出すチャンスが見つかるはずです。

